dance
ダンスに関する文章です。
「Dead Souls」作品コメント [ dance ]
大橋可也が日本女子体育大学の学生に振付けた作品「Dead Souls」の当日パンフレットに寄せた文章です。
タイトルはジョイ・ディヴィジョン(1976-1980)の同名曲からの引用です。ジョイ・ディヴィジョンの名称はナチスの慰安所に由来しているそうだが、福島第一原発で多大なプレッシャーの中で働く男たちを思うと、慰安所の一つもないと廃炉までの数十年間、彼らのモチベーションを維持することができるのだろうかと、不謹慎なれど思う。
あらかじめ失われたものたちへ [ dance , spring ]
ゼロ年代が終わり、テン年代が始まったとしても、ここに新たな希望などあるはずもなく、失われた10 年は、失われた15 年となり、さらに20 年になろうとし、これから成人を迎える若者たちは、もはや失われた世代ですらなく、あらかじめ失われたものたちと呼ばれるだろう。
さて、「春の祭典」。春の光は凍りついた大地を解かし、雪解けの水は地表の堆積物を洗い流す。今回の舞台では、とある地方都市を背景に、2 つの家庭、彼らを取り巻く人々、外部からの訪問者が登場する。閉ざされた共同社会の価値観が崩壊し、外部から押し寄せてくる価値観に覆われていくさま。ここでは私たち全員が生け贄として選ばれている。そう、これは今私たちが暮らす日本社会の縮図でもある。
私たちを覆う閉塞状況から抜け出すには、もはや幻想でしかない過去の価値観や制度にすがるのではなく、あるいは、美辞麗句に飾られた救済思想に身をゆだねることではなく、この閉塞状況をただ見つめ、立ち向かい、新たな枠組みを模索していくほかはないのだ。
「春の祭典」は何も答えなどは用意していない。しかし、この体験が、あらかじめ失われたものたちにとって、次なる一歩を踏み出すための刺激になることを、切に願う。
劇場入りを前日に控えて
大橋可也
「春の祭典」の当日パンフレットに掲載した文章です。
作品の設定について触れていますが、これはあくまで作品作りのためのフレームです。当日パンフレットの文章を読もうとする人、つまり作品を理解するための付加情報を欲している人にとっては、作品理解のためのフレームとしても役立つと思い、掲載した次第です。作品のテーマそのものではないので、誤解なきよう、お願いします。
大橋可也×佐々木敦×西中賢治『春の祭典』鼎談(司会・構成:黒川直樹) [ dance , spring ]
大橋可也×佐々木敦×西中賢治『春の祭典』鼎談がCINRA.NETに公開されました。
「春の祭典」の行く末を占うトーク、黒川直樹による構成も合わせて、お楽しみください。
「春の祭典」チケット料金について [ dance , spring ]
「春の祭典」は生け贄のお話なわけだけが、今の僕たちにとっての生け贄は誰なのだろうか。
それは若者だよね。単純に若い人といったほうが適切かもしれない。
「春の祭典」のチケット料金設定について、その意図を説明します。
帝国ペーパーにも寄稿していただいた赤木智弘さんの第一作のタイトルは「若者を見殺しにする国」なのだが、今の日本は老人たちが既得権にしがみつき、若者を食い物にしながら、自らの死まで逃げ切ろうとしてる状況だろう。
その状況に若者たちが自覚がない、あっても仕方がないことと受け入れてしまっていることが問題、大きな問題だと思う。
というわけで、今回は若者にやさしい料金設定を導入しました。
10代は1000円、20代は2000円、(中略)、50代以上は5000円となります。
若者にやさしい、ということは、老人にやさしくない、ということなのだが、老人にやさしくしなければいけないという発想は、選挙権を確保したい政治家のためのものであって、僕たちがそれに侵される必要などはないのだ。
前回の公演までおこなっていた20000円から0円の料金設定を辞めた理由はそれなりにあるのだが、別の機会に言及します。
不思議なのは、コンテンポラリーダンスを標榜するアーティストの公演で、僕たちのような料金設定をおこなうケースが皆無なことだ。別にまねしなくてもよいのだけれども。
以前、僕は、「公演をおこなうことは社会運動をおこなうことである。」と言ったのだが、僕たちが社会に対して直接的に働きかける機会が公演なのであり、その料金設定は僕たちがいかに社会に関わろうとしているかを表明する絶好の、限られた、機会ではないか。
どのようにチケット料金を設定するか、それは即ち、どのように社会にコミットしようとしているか、というアーティストの意思表示に他ならない。
若者を見殺しにしない、それが今回の僕たちの意思表示です。
緊急:「事業仕分け」に対するパブリックコメントをお寄せください。 [ dance ]
「事業仕分け」については、各所で話題になっていますが、芸術文化関係の事業についても事業仕分けの対象になりました。
僕たちの身近なところでは、芸術文化振興基金の政府分は廃止、在外研修の見直しなど、今後の舞台芸術の活動に大きな影響が出そうな内容になっています。
これら仕分け対象となった事業について、文部科学省がパブリックコメントを募集しています。〆切りは12/15となっていますが、11/19におこなわれる行政刷新本会議に間に合うことが望ましいとのことなので、少しでも日本の芸術を大事にしたいと思う方は、今すぐご意見をお寄せください。
コメントの宛先などの詳細は以下のリンクをご覧ください。
行政刷新会議事業仕分け対象事業についてご意見をお寄せください
文化関係の事業は以下の通りです。
・文化関係(1)―(独)日本芸術文化振興会
・文化関係(2)―芸術家の国際交流等(芸術家の国際交流、伝統文化こども教室事業、学校への芸術家派遣、コミュニケーション教育拠点形成事業)
大橋可也『深淵の明晰』最終公演前インタビュー [ abyss , dance ]
京阪神を中心にしたダンスの情報サイト「dance+」に古後奈緒子さんによる大橋可也のインタビューが掲載されました。大橋可也がダンスに取り組むようになったきっかけから、「深淵の明晰」の見どころまで踏み込んだインタビューになっています。是非ご覧ください。
「深淵の明晰」京都公演当日パンフレット原稿 [ abyss , dance ]
「深淵の明晰」東京公演で配布している当日パンフレットには、大橋可也の文章は載せていませんが、東京公演に先立っておこなわれた京都公演の当日パンフレットに掲載した文章を公開します。
希望に満ちた若き日を過ごした全共闘世代は、結局のところ日本を変えることはなく、後続の世代に支えられた年金を得て、豊かな老後を過ごすことだろう。希望のない日々を過ごす若者たちは、「ナンバーワンよりオンリーワン」という価値観に飼い馴らされ、現状を変えようとしないまま生きていくことだろう。
いかに新しい政権が「友愛」を説いたとしても、小泉・竹中改革にこの国の現状の責任を押し付けたとしても、グローバリゼーションの荒波は絶えることなく、僕たちの足元まで押し寄せ続ける。僕たちにできることは、その波に抗することではなく、流されてしまうことだ。流された果てに打ち上げられたどこかの海岸で、光り輝く原石を見つけることが、それは携帯電話の残骸かも知れないけれども、たぶん一つの冴えたやり方ではないだろうか。
キマイラの橋 [ abyss , dance ]
『深淵の明晰』チラシ裏面に掲載されている、鼎談:大橋可也&ダンサーズ「キマイラの橋」を公開します。
「深淵の明晰」京都公演 | 「深淵の明晰」東京公演 | 「深淵の明晰」福岡公演 | 「深淵の明晰」伊丹公演
檀) 本日はお集まり頂きありがとうございました。まずはじめに、大橋可也&ダンサーズとの関わりを教えて下さい。
江) 私は2003年より大橋作品に出演するようになりました。現在カンパニーの中では最も古参のメンバーです。ダンサーとしてはブランクのある時期もありますが、基本的に03年以降海外公演を除いて全ての作品に出演者として或いは観客として立ち会ってきました。
黒) 『帝国、エアリアル』のペーパーデザインを任せてもらったのが、大橋可也&ダンサーズとの出会いです。以来、デザインでは『帝国ナイト』『Bleached』のフライヤーを、文章では『Black Swan』『帝国、エアリアル』を書いてきました。
檀) 1996年に森下スタジオで行われたワークショップで知り合いました。大橋可也&ダンサーズへは一作目と三作目に参加しています。カンパニー結成以前も含めて、比較的初期の作品に立ち会ってきました。
■「大橋可也&ダンサーズ」結成以前 ~この惑星は僕の居場所じゃない~
黒) まずグループ結成以前の活動である『ミヅチ』の話から行きましょう。大橋さんが一人でやっていたんですか?
檀) 踊り手は一人だけ。他に映像の"NEO VISION"が一緒でした。大橋はイメージフォーラム付属映像研究所で学んでいて、その頃知り合ったようですね。
江) 彼らはバニョレ参加作品(『Today Your Love,Tomorrow The World /2000』や『明晰』のときも係わってますね。初期の頃、メディアはどう使っていたんですか?
檀) 大橋可也の生の踊りをビデオカメラで撮影しながら、デジタルエフェクトでサーモグラフィのように変換します。それを、舞台と同時進行で大スクリーンに映していました。一例に過ぎませんが。
江) この頃はテーマ性よりも、メディアとダンスの実験的な関わりを追求していたんですね。ちょうどダンスの世界で映像が盛んに使われ出した時期と重なります。Windows 95が発売されてITが急速に身近になってきたことも大きいのかも知れない。
黒) いまも音と映像を使う作品はありますね。その頃、原型ができたのかも知れませんね。
檀) 搬入口を開け放して現実世界を借景に使った作品(『明晰の鎖/2008』)がありましたが、映像の方も舞台上の世界のひとつの位相として取り上げるのが、近年の方向性だと思います。しかし初期のころは「マルチメディア」志向でしたね。
江) まだ動きに暴力的な要素はなくて、むしろ自発的にダンスらしく動いていたようですね。
黒) それがフォルムを意識したダンスだった、と。
江) (好善社の)和栗由紀夫は特にそう。
檀) 好善社にはあの当時五人くらいのメンバーがいましたが、一人一人の身体の質感がかなり違っていました。その中でも際だって異質だったのが大橋可也。宇宙人みたいで、デイビッド・ボウイの「地球に落ちてきた男」を彷彿とさせましたね。
江) 中性的ですよね。
黒) 舞踏の人は「理想的な舞踏家像」に重なるために稽古をするのでは? という先入観もあったのですが、カンパニーごとにカラーがあるんですね。
檀) 大駱駝艦や山海塾にはそういう印象がありますね。体格差こそあれ、メンバー全員のテイストが同じで区別がつかない。後頭部の形で舞踏手の識別をする、みたいな(笑) でも好善社は一人一人全然違う。東雲舞踏にもそういう要素が受け継がれています。
黒) 檀原さんはグループ結成以前から大橋さんを見ていて、参加してみたら今までと全然違うのでビックリしたんじゃないですか?
■第一期 ~ダンスからの脱却を模索。手探りで歩きはじめる~
檀) 創世時代は全然ダンスの稽古らしいことをしなかったんですよ。匍匐前進とか、走っていって壁にぶつかってまた走る、とか。特に匍匐前進はかなりやらされました。「大橋可也といえば匍匐前進」というくらい。「かかとをあげるな! 付けたままで前進して!」などと注意された事を憶えています。今までにない新しい作風を確立しようと試行錯誤していたんでしょうね。
江) 作品を作る前段階で「こういう事をしたいんだ」という説明が全くなかった(笑) 何をやるかも分からず訓練をさせられて……。でも、できあがったものを見ると「初めから明確なイメージがあったんだろうな」と感じました。
檀) 最初から「非ダンス」のようなことをしよう、という狙いはあったんでしょうね。大橋はかなり踊れるダンサーですが、あえてダンスのボキャブラリーを封印していましたから。記憶している限りでは、バニョレのとき、ミウミウとのデュオでコンタクトインプロのような動きを指示されたときくらいですね、ダンスらしい動きを要求されたのは。結局その動きは却下されましたけど。「ダンスとはなにか、問いかける」という姿勢はあったんでしょうけれど、まだとっかかりが少なくて模索していた段階だったのでは。
黒) ダンスの手がかりを既知のダンスフォームに求めることなく、匍匐前進から始めたっていうことがすごいですね。
檀) 初期の作風は非常に性的でしたね。バニョレまでは男女の性だけでなくて、同性愛も含めたセックス。とくに旗揚げ作品はメンバーが全員男で全裸だったから、ホモっぽかった。密着する場面もあったし。
STスポット(横浜)の「ラボ20」での上演でした(『Revolution in summer/男根主義でいこう/1999』)が、オーディションのときはまだメンバーを集めていなかったようで、大橋がひとりで乗り込んだそうです。審査中は、踊らずにずっとしゃべりつづけていたと聞いています。キュレーターは伊藤キムでした。最初の頃はバカなことばかりしていて、ロマンス小林が「うちのポチは目玉焼きが好きなんだよ」などと言って、舞台にカセットコンロを持ち込んで料理をし、観客に食べさせたり。
後日伊藤キムと話したとき、「今の時代にこんなバカなことをしている奴らがいるとは思わなかった」と言われました。あの路線を突き進んでいたら、ゴキブリコンビナートみたいになっていたかも知れない(笑)
江)黒) (笑)
江) 女性陣は二作目(『Search and Destroy/1999』)からの参加ですが、ゲーム形式でラウンドガールが持つようなプラカードを上げ下げしてみたり、かなり現在と違う感じでした。
檀) 全裸で四つん這いになった大橋が、白いピンヒールを履いた堅田千里(東雲舞踏)に跨られていたり、まだおバカな路線でした。引いている観客も結構いて。当時のキャッチは「ハードコアダンス」だった。……そうそう。スカンクのバンドが新宿のライブハウス「LOFT」に出演したとき、僕らはバックダンサーとして踊ったんですが、対バンした方から「随分コアですねぇ」と言われてました。
江) バニョレ時代も裸であるということと、非ダンスであるということが取りざたされました。それから身体をぶつける、ということから「暴力」や「セックス」といったことが言われ始めました。
檀) バニョレのとき読んでいたテキストは『レイプ・男からの発言』(ティモシー・ベイネケ・著)。もろに性的。
江) 現在の大橋の作風で、このとき既にあったのは?
檀) 密室感、無機質、ダンサーに上下関係がないフラットな感じ。「同時多発的な動き」もあったといえばあった。ただ社会批評性という側面はまだ弱かったですね。
第一期のハイライトはバニョレへの参加ですが、うちのカンパニーだけフランス本国より選考の通知が来たんですよ。よそは全部ジャパンプラットフォームから通知だったのですが。雑誌『ダンサート』のバニョレの記事に、僕たちだけ載っていなかったり。異端でしたね(笑)
黒) 第二期に入ると、かなり変わるんですか?
檀) バニョレを境に大きく変わり始めます。バニョレ参加作品は初期の集大成ですが、第二期の萌芽もみられます。この作品の稽古中、"NEO VISION"のメンバーが「大橋作品への信頼が回復しました」と。ダンサーズの作品ではじめて映像を取り入れた作品でもありますしね。
■第二期 ~3年の休止期間を経て、再び活動開始。振付家として同時代の身体への挑戦~
江) 『Hardcoredance Highschool 1st session/2003』は少し作品自体が宗教団体を彷彿させるようなところがありましたよ。
黒) 宗教団体? それはオウム真理教とかを意識したってこと?
江) そうですね、創作段階では大橋が教祖でミウミウが幹部、他三人のダンサーが信者たちという設定で作りました(笑)
檀) 大橋が教祖って…(笑) 似合うねー。
江) はい。でも実際には大橋がもう一度自分で創作を開始する上でハードコアダンスってなんだ? という問いを自らに、また観客に問いかけた作品だったので社会問題などをテーマにしたわけではないと思います。振付も第一期までと同様にひたすらヘッドバンキングしたり叫んだりというシンプルなものがメインで、女が3人並んでパンを一斤ずつかじったり…で、最後に大橋が前に出て踊るという内容だったのでまだ第一期と同様、模索した作品でした。また04年に『あなたがここにいてほしい』のグループバージョンが発表されますが、私が出演した作品の前半部分は舞踏譜を使って性器やセックスをあからさまに表現し、やっぱりひたすら走ったり抱き合ったりと少し馬鹿げた内容でしたので何か大きな変化があったとは思えません。
檀) 確かに舞踏の表現ってどこか男性的な笑いがあるよね。下品なネタが多い。
黒) ひょっとして性器を晒すとか?
江) そういうことも昔はしてたと思うんですが、このときはパンツの中に手を突っ込んだりアナルに拳を押し付けて興奮したり…とそういったものでした。
檀) なんか悪い言い方をするとちょっと体育会的なノリが舞踏にはあるよね。
江) そうですね、勢いが必要ですね(笑) で、そのグループバージョンの後半部分、大橋とミウミウのデュオが後にコンペに出展したりツアーに回ったりなどして大橋可也&ダンサーズの代表作『あなたがここにいてほしい/2004』デュオバージョンともなるんですが、やはりこの作品が大橋作品の第二期の始まりと言えるんだと思います。
檀) 確かにグループバージョンのほうは過去の作品と似ている印象があったな。でもデュオ作品になって作品もぐっと締まって見えた。今までとは違い、とてもシンプルな構造になってクリアになったよね。特に5人バージョンのときは檻ももっと使い方があってもいいのにと思ったりしたけど、デュオ作品になって檻自体なくなったし。とにかく緊張感が出た。
江) そうですね、いろいろな意味で見づらい作品だったと思うんです。美術があると具体的な設定を観客に与えてしまって、それ以上の想像する余地がなくなる危険性がありますね。特に檻は「=監禁」 というようにイメージが強すぎる。具体的なストーリーがあるようで作品の前半後半のつながりもあまりはっきりしていなかったし、観客もあまりよくわからなかったんじゃないかなと思います。前半が無くなり檻が無くなって身体がクリアになり、観客も絵には描かれない様々な背景を想像したり関係性を見ることができたから緊張感も出たんだと思います。これ以降に発表された大橋可也&ダンサーズのどの作品においても他者との距離や関係性・緊張をどのように振付するかはとても重要なポイントになります。これは第一期とは違う大きな変化だと思います。あと大きな変化といえば、この作品がNYのキッチンで上演された際に向こうの批評家がこの作品を次のように書いたんです。
―都市生活は、見ることと見られているとの認識の間に急速な行き来を含んでいる。時々、一瞬の間さえあいまいになりえる。「あなたがここにいてほしい」での身悶えやそれぞれのもがきは、異なった物語に巻き込まれた人々の近くにある不快感を暗示しているかのようだ。このダンスは、暴力性を含むことで熟されている。大橋の顔の表情の幅、彼が座って我々と向き合っている位置、彼のスーツと激しいサウンドデザインは、地下鉄の設定をほのめかしているかのようだ。大橋は1995年に起きた東京の地下鉄サリン事件に言及しようとしたのかもしれない。(中略)「私は虐待には特に興味はない」大橋は言う。「しかし、普遍的な暴力には興味がある。」
余越は、「あなたがここにいてほしい」は、「東京のエッセンス」を捉えていると言う。(中略)彼らが意識的に都市的であろうとしていると思わないが、孤立とコミュニケーションの強い存在があり、私には、それがどういうわけか都市と結びつくのです。―
【The Brooklyn Rail / ブルックリン レイル 2005年11月号「ダンスと都市的経験」Emilr LaRocque】
つまりこれこそが大橋の考えてきたハードコアダンスの真髄だと思うんですけど、この作品を通して「私たちに必要な踊りとはなにか」「何が同時代の身体なのか」、それらを考える上で私たちが都市に生き、常に防犯カメラに監視され、過剰な情報化社会の中で無意識のまま他者からの視線に脅かされているということをまず意識しなければならない。それを考えるきっかけになったとも思うんです。
黒) 社会性を明確に浮かび上がらせようという演出の下に、ダンスが作られるようになっていくんですね。
江) ええ、でもまだ私たちダンサーは創作段階で大橋からそういう意図があることは説明されてなかったので、相変わらず何をやらされているんだろう…と疑念を抱いてました(笑) でも、私もはじめてデュオバージョンを見たときは衝撃を受けましたね。作品に完全に揺さぶられました。だから何をやらされているのかはまだよくわからないけど、大橋を信じてそれ以降もカンパニー作品に出たいと思ったんです。
黒) この頃、メンバーの入れ替えはあったんですか?
江) 基本的には大橋・ミウミウを中心にして他は作品ごとに出演者は替わりました。スタッフは初期の頃から関わっている方もいるのですが、ダンサーズとしてのカンパニー体制はまだ確立しておらず、毎回こちらから声を掛けたり或いは逆にダンサーのほうからコンタクトがあったりという形で出演者は流動的に替わっていきました。でも『サクリファイス/2005』に出演した皆木正純はそれ以降全てのカンパニー作品に出ていて、大橋可也&ダンサーズには無くてはならない存在だと思います。
檀) 彼は一見とても普通でダンサーっぽくないけど凄い変な跳躍とか出来たりするよね。
江) そうなんです。皆木はもともと役者なんですけど、彼の跳躍とか痙攣は神掛かったものがあります。一緒に踊っていてこちらがハラハラするくらいギリギリなところまでやってしまうんですよ。実際に骨を折る大怪我をしたこともあったんですけど…。
檀) (笑) 彼、『Black Swan/2008』の横浜公演のとき、海に落ちそうになってたよね。
江) 皆木が出演するようになってから大橋の振付も大分ハードコアさが増したところがあります(笑)
檀) 多分、その『サクリファイス』の頃からだと思うんだけど、作風も少し変わってきたよね。衣装も裸とか下着ではなくて日常的な洋服になったし。
江) そうですね。その前の『シスターチェーンソー/2004』からきちんと服を着るようになりましたね。大橋自身「本当は裸が一番の衣装」とこの頃はまだ言っていたと思うんですけど、作品に普遍性を持たせることを考えると観客の姿になるべく近づけることも考えたんでしょうか? 衣装はどんどん日常的になっていきましたね。作風ということでいいますと、これは振付方法なんですけど激しい連続運動や舞踏譜以外のネタとして日常的な動作が沢山取り入れらるようになりました。動きのフォルムに拘るようになりました。その際、ある一つの日常的動作をダンサーそれぞれの個性や技量に合わせて非常にミニマルなものにしたり、大幅にデフォルメしたりして振りを展開していくんです。
檀) 初期の頃と比べると踊りに大分幅が広がってきたね。僕が出演していた頃は「走って」とか「叫んで」とかシンプルに指示されるだけだったからね。
黒) 先日稽古場を見学させてもらって感じたんですけど、大橋はダンサー一人ひとりとのコミュニケーションを取る時間を非常に大事にしていますよね。「最近、生活どう?」とか聞いたり。そういうのって初期の作り方、「これをこうやって…」と指示をあおるだけのやり方とは大分違うんじゃないかなって感じました。
江) そうですね。他のダンスカンパニーがどのように作っているか、あまり知りませんが今の大橋可也&ダンサーズの作品は基本的に代役不可ですね。他の人が踊ると全く違う作品になってしまう。他の人が踊る場合はおそらくまたその人に合わせて振付を調整をしていくことになると思うんです。多分、タイトルも変わっちゃいますね。
黒) 一人ひとりとのコミュニケーションのやりとりが大事だから2007年以降はオーディションをして、きちんとカンパニー体制を整えようとしたんでしょうね。普通ダンス作品を見るときってこの振付が凄いとかそれを踊っている人たちの身体が凄いっていう印象をまず受けると思うんだけど、大橋の場合はそれぞれの個性に近づけて作るから単に上手だねとか綺麗だねっていう見方とは違ってユニークだなと思う。
檀) そうそう、それを聞いて思い出したんだけど一般的なダンス作品を見るとき、観客はダンサーとグルーヴ感を共有していると思うんだ。だから開演してすぐに作品と同調して、気持ちよくなれる。でも大橋の場合、演劇のように長い時間を経てやっと最後にカタルシスに到達するところがあるよね。そういう意味でとても構造的だなと思う。
江) そうですね。確実に時間の経過を計算して作っていますね。ダンス批評家の木村覚が『CLOSURES/2007』について次のように書いています。
―大橋可也の作品が見る者を唖然とさせるとき、そこには独自の「時間」が出現している。だからぼくにとって、大橋は時間の作家である。観客をもてなす何らの物語も、舞台上の人物による自己告白もなく、経過する時間。受け身の観客に満足を与えるイリュージョンのヴェールはあっさりはぎ取られ、むき出しでからっぽな、裸の時間が、劇場の閉じた空間に放り出される。 ぼくはそこで、うぬぼれた観客として安穏とすることは最早許されず、出来事の目撃者ないし証人として立ち合うなんて余裕も与えられなくて、ただただ時間が生まれる空間を共有する一種の共犯者のような気持ちでひやひやさせられている、巻き込まれた自分に気づく。観客の見る(体験・体感する)のは、自分も加担してしまっている更新中の時間それ自体なのだ。―
【wonderland 2007年1月27日「コントロールを遊ぶむき出しの時間」木村覚】
もうこれは大橋以外の人間には作品が完成して幕が開けてみないと分からないんです。踊っている人間は作中あまり高揚しないよう指示されたりしますからね。それが如実に表れたのは明晰2(『明晰の鎖/2008』)の中の『ダウンワードスパイラル』だと思います。
■第三期 ~メンバー入れ替わりを経て、明晰3部作が完結へ。公演に際しイベントやペーパーを企画するなど、ダンスシーンを越える試みも始まる~
江) 構造的な作品の完成度として考えると明晰1(『明晰さは目の前の一点に過ぎない/2006』)が大橋可也&ダンサーズの第三期のスタートだと思います。この頃になると大橋も作品を作る前段階でダンサーたちにこれから自分たちがどういう作品を作ろうとしているのか、明確に説明するようになりました。ダンサーは相変わらず流動的でしたが出演者の半分は前作から続投していたのでコミュニケーションも大分取れていたと思います。大きな変化と言えば、音楽がスカンクから舩橋陽に替わったこと、久々に本格的にメディアを用いた作品を作るようになったことです。
黒) 明晰2で第三期の中核になるメンバーが定まったんですよね。どういう風に集まったんですか?
江) このときはオーディションを一般公募したんですが、来た人が全員採用されました。
黒) ええっ、 オール・ウェルカムだったんですか!?
江) はい…(笑) 正直私はそんな緩い方法でカンパニーが新しくなることに難しさもあるかと思ったのです。でも大橋のダンサーとのコミュニケーション能力が上がったんでしょうね。いつの間にかとてもいい雰囲気になっていました。
檀) 明晰の1と2の間には、イタリアの6都市を回った『Journey Beyond the Clarity/2006』ツアーが行われたんですよね。
江) 大橋は今でも時々「舞台環境からダンスを発想するようになったのは、公園や教会の広場をステージにしなくてはならなかったイタリアツアーの経験が大きい」と話しています。『帝国ナイト/2009』短編をリハーサルしに「青い部屋(渋谷のライブハウス)」に入ったとき、ガラス張りの小スペースを見た大橋可也が「この中で踊ることにしよう」と言ってから15分くらいで作品が演出されたこともありました。
黒) 15分? ホントですか? あの作品って解説もセリフも音楽も一切なくダンスだけを見せてくれたんですけど……あ? あれ? あれ? っていつのまにか始まってた作品を数分見ていただけなのにまず鳥肌が立ったと思ったら息がうまく出来なくなるような感じになってることに気付いたんだけどその頃には胸が詰まってるのとダンサーが踊ってる劇中の境遇とそこに生きてる人たちの感情とかにシンクロしてしまってる自分いるなんていう体感は初めてだったんで戸惑ってたんだと思うんですが、え? え? こういうときって涙が出そうになるのかヤベーなって感じで、なんだろう、いま何が伝えられようとしているか、いま何を起こそうとしてこの人たちが踊ってるのか、いま大橋可也に何を見せられようとしてるのかってことが言葉じゃなくダイレクトに伝心されるなんてことあるのかヤベー、ヤベー、ヤベーって気持の中では呟かされてるんだけどそれを声に出した途端に、硝子空間の意味だとかその薄くて脆い危機的な物質感をまとったダンサーのパフォーマンスや作品のメッセージを皹にしてしまうんじゃないかって躊躇ってた、でもホントは苦手なんです一度きりとかその場限りの何かを重んじたりするのって……
檀) 信仰めいててイヤだっていう感じかな。
黒) そうですね。にも関わらず「こんなスゲーの二度と無いからよく見ておくんだ」って啓示めいた勘を途惑いの吐露が汚してしまうんじゃないかって高ぶりが込み上げてきてて息がじょうずにできない、言いたいこと言えない、喋りたいけど喋れない、動きたいが動けないっていうこの有様ってまさにダンサーが数本の蛍光灯の明かりだけに浮かび上がる硝子張りの小さなスペースに詰め込まれた踊って踊らされて踊ることになってる様相と同期していたフロアには観客がびっしり座っていました。立てかけられた縦長の蛍光灯に照らされた硝子一枚に囲われた狭い部屋に家畜みたく詰められた14、5人のダンサーが満員電車とか密室に生きる息苦しさみたいなものを感じさせてたんスよね、硝子に仕切られた空間が建物とか乗物に見えてくるんです。しかもあの硝子一枚が作品に効いてたんだなって思ったのは作品を見終えて数時間経ってからだったんですけれど、あ、仕切りが硝子だった、ガラスに隔てられてる囲われてる叩けば硝子なんてすぐに割れよう、ガラスってあるようでないようなモノだろう?それは砕けば刃物のようにだって握れようがこの場において硝子はその素材が透明であるからこそ「見透けているからはっきり眺められる貴方たちの姿なのにこのままじゃけっして触れることができない」という隔絶の現実感として生々しくありました。あの硝子、そのウチに作品のはじめ異様な静けさを揺らしていたダンサー2人3人の揺れが同調していきます。ところが同調していく2人3人の揺れなのだから集団が成されてたっていいはずなのにダンサーに共感や同意が果たされることはなくって。
江) 踊っていたので分からないんですが、バラバラでしたか? ダンサーが。
黒) ええ、部屋の中を眺めてても「彼ら」とか「彼女ら」という感じはなく、もしやダンサーは魂の温もりを消失したか盗まれたか劣化させられたことによってああなったんじゃなかったか? 硝子小屋を覗けばそこに筋肉質の太い、タイトな肌着に包まれた、まとめられた長髪を廻す、細見の、長身の、むき出しの、大粒の汗を光らせた、ぶつかりを痣とする、それぞれの体に醒めてない何かがあるように感じた。次いでダンサーが生まれ過ごしていた時間のどこかには彼ら彼女らが「醒めてた」瞬間があったということですから「過去」に気付くでしょう? それで作品の上演は、そういった過去を見せる現在でもあると同時に硝子小屋は電車のようにも見えたので、そうか、この乗物は未来に向かってもいるって、つまりおれはここで過去から未来が一針の虫ピンに喉仏を貫かれて宙に止められたという妄想と硝子に囲われた小屋で衝突を続けるダンサーの濃縮された意味が苦しい、苦しい、苦しい、ダンサーは核分裂していく状況反射で爆発的な暴走を果てたそういえば密室で繰り返された十数人の衝突は乱闘にすら見えなかったなんてどういうことか。みんな人なのに。そのぶつかりが乱闘に見えない。なんて。どういうことか……終幕に近づきダンサーは充電の切つつあるロボットみたく……弱まってく……横たわり荒げる息に添って膨らみ萎むダンサー……それでみな床に絶えたけれど、あれから数日は「あの作品ってなんだったのか……」って引き摺っていたし、短篇の上演時間のショートネスも、硝子の密室とか満員電車っていう都市的な象徴のスケールと詩的に共鳴していて凄いよかったので、まさか! たった15分で演出されたとは!
檀) 「青い部屋」での短篇に大橋可也は出現しましたか?
江) 舞台に上がったのはダンサーだけでした。でも思い出してみれば彼が劇中に現われる作品のほうが多そうです。
檀) 『CLOSURES/2007』のとき、非常に効果的な演出が試みられているって思ったんです。演出家がわざわざ舞台上に上がって<自分が作品世界をコントロールしている>ということを表明する。それが一転、演出家という権力の失墜、あるいはシステムの反転を思わせて終わる。現代アート的で興味深い演出だな、と。
黒) さっき青い部屋での作品を賛じたので、一つ観客のコメントを紹介させてください。
―2008年2月11日 大橋可也&ダンサーズ『明晰の鎖』02/09-11吉祥寺シアター。大橋可也&ダンサーズの公演を拝見するのは初めてです。“現代社会における身体の問題を追求し、ダンスの必然性を問う”スタイルに興味を持ちました。(中略)「よくわからなかった」というのが全体の感想です。(中略)眠くなっちゃうことも多かった……―
【「しのぶの演劇レビュー」2008年2月11日】
これは演劇のレビューサイトを運営している高野しのぶさんによるレビューです。彼女は文中で細かい作品分析されていたり、
―客席でじーっと何かを見つめている時間は、豊かな思索の時間だと思います。(中略)演劇だとセリフや意味がストレートに言葉(音声)で伝わってくるので、“思索”といえるほど深い心理に入り込むことって少ないんですよね―
という心理を書いている観劇リテラシーの高い方ですが、それでも“よくわからなくて眠くなる時間もあった”のだと。大橋可也&ダンサーズの舞台は観客との安易な共感を棄てたところから始められている。それは現代におけるコミュニケーションを真剣に考えた結果でもあるんだけれど、パッと見れば難解に感じるかもしれない。でもハマる人はすごくハマる。自分の人生は最終的に自分で決めるんだという人には特別な機会になるんじゃないかと思います。そういう性格であるが故に迷いの時間を過ごしている人にとっても。
■観客、批評、私たち ~言葉で作品世界を咀嚼する、ということについて~
檀) 黒川さん、大橋に出会ったのは佐々木敦さんの批評の講義だったんですよね? ダンスを書くということについて、なにか考えてることってあります?
黒) んーと、そうですね。初めてダンスについて書いたのは『Black Swan』で、それは作品を形而上学的な刺激のある時間として受け止めていく文章だったんですが、後になってあの作品に「夫婦の関係」というモチーフがあったと聞いて絶句し(笑) また『Bleached』には「白色レグホンと高度成長期」という背景があると知ってびっくりしたり。
江) それはダンサーやオーディエンスを導き入れるための物語ではなく、あくまでもダンスを作っていくきっかけとして要請される世界観なんですよね。
黒) ああ、そうか。世界観を伝えるためのダンスではないんですね。自分でも批評を書き始めたのは、作品や作家を見下ろした位置から見識を押し付ける暴力的な文章にすごく不満があったからだったんです。まあそんなこと気にしてるのはおれだけなんだろうと思ってたら、批評や批評家への強い不信を訴えるダンサーやアーティストって少なくなくて。
檀) 作品の難解さ、そして批評テキストの抽象性の高さは、『帝国、エアリアル/2008』で唄われた「生きづらさを感じる人」が鑑賞する上でのハードルの高さに繋がっていますね。
江) 『明晰』シリーズのファンが社会的/言論的だった『帝国』の方向性に違和感を覚えたという話も聞きます。
黒) ただ、批評には批評の可能性があるし、すべてのアートがそうであるようにダンスも言葉と切り離せないでしょう? たとえば振り作りのモチーフひとつ確かめてみても、それは言葉で認識されている世界観。だから、言葉を発することが作品の可能性を乏しくさせることもあるって自戒しつつ、作り手にとって刺激的な受け手でいるためにはどういう書き物がやれるか考えたいし、アーティストには未知との遭遇を経験させて欲しいから、こちらもアーティストに未体験を還せるような何かを書こうと思ってます。檀原さんは作家として批評についてどう考えてらっしゃいます?
檀) 「辻調理師専門学校」の辻校長の伝記小説を読んだとき、「料理評論家はなぜ必要なのか?」という話が出てきたんですけどね。トップシェフは忙しくて自分と付き合いのある店にしか食べにいけないらしいんです。業界のトレンドや新しい流れを、時間が取れない一流のシェフに伝えるのが評論家の務めだって。それはダンスの世界でも同じじゃないかな。
江) その一方で、ダンスシーンの内側だけに留まらない活動をしていくためには、ダンサー以外の人たちにも届く言葉が必要ですよね。
檀) では、最後に明晰3『深淵の明晰』への期待を一言づつ。
黒) 創作モチーフの翻訳や注釈に留まることない踊りでもって、踊り手が作品を内から砕き、ダンサーとして孵る瞬間を目撃しに出かけます。
江) 明晰2は確かな手ごたえがありましたので是非それを超えてほしいですね。今回対談するにあたって久々に過去の作品を見ました。そうしたら、やはり進化した部分も沢山見えたんですけど逆に置いてきてしまった面白さも見えたんです。ダンサーの身体の個性という点では過去のほうが際立ってよく見えていた気もします。いまの匿名性の高い振付の中でもダンサーそれぞれがもっと身体を主張し合ってほしいですね。
檀) 観客の意表をつくような、あらたな次元への萌芽が見られるんじゃないかと、密かに期待しています。
(2009年6月21日 東京・森下スタジオにて)
檀原照和
「土地にまつわる習俗」をテーマにした作家。2006年に夏目書房より『ヴードゥー大全』を、2009年に『消えた横浜娼婦たち』(データハウス)を発表。大橋可也&ダンサーズへは一作目と三作目に参加。
江夏令奈
大橋可也&ダンサーズのメンバー。1980年生まれ、早稲田大学第二文学部卒。在学中、和栗由紀夫と出会い師事する。様々な舞台を経て、2003年より大橋作品に多数出演する。現在第二子妊娠中のため、ダンサーズ活動は産休中。
黒川直樹
「誰だ!なんだ!この作文は……」と哂った教授が秘密枠での誘いを決めてくれたことで入学が叶った大学でデザインと書き物を始める。水木しげるとゴダールと村西とおるを尊敬する現代詩のトリル。BLOG「仮)黒川直樹の妄想劇場」支配人でもある。
大橋可也と『明晰の鎖』について [ abyss , chain , dance ]
『深淵の明晰』のチラシに掲載している、「明晰」第二作『明晰の鎖』についての石井達郎さんの文章です。
「深淵の明晰」京都公演 | 「深淵の明晰」東京公演 | 「深淵の明晰」福岡公演 | 「深淵の明晰」伊丹公演
大橋可也と『明晰の鎖』について
石井達朗(舞踊評論家)
大橋可也は日本のコンテンポラリーダンスのなかで、特異な位置を占めている。彼の作品はストイックなまでに「踊る」ということを排除して、身体の現前性に、身体が今ここにあるということに、こだわる。そこから見えてくるのは「日常」という表層の下に隠された、抑圧された衝動であり、抑えることのできない暴力であり、男と女の間のコミュニケーション不能なジェンダーの壁である。そこに土方巽以来、日本の舞踏やコンテンポラリーダンスのなかで育まれてきた、ある種の身体観を見ることも可能だが、大橋の作品の注目すべき点は、身体の動きそのものばかりでなく、空間全体に意識を張り巡らせたような現代的な演出にある。身体の震えが、劇場空間のすみずみにまで波及してゆくと、今度はダンサーの身体が空間の囚われ人になったかのように出口を失い、硬直する。
上演時間110分、3部構成の『明晰の鎖』は、そのような大橋の仕事の集大成といえる作品である。前半、舞台後方は、劇場の外の街路に向けて扉が大きく開けられたままであり、観客は踊り手が動く「虚構」と、表通りを行き交う人々の「現実」を交錯させるようにして同時に見ることになる。後半、この扉が閉められた後に展開する女たちの緊張した動きや微妙な表情、そして第3部でビデオモニターにより次々にクローズアップされる女たちの姿態。ここでは虚構も物語も霧消してゆき、女たちの一瞬一瞬の身体の生々しさのみが連鎖してゆく。それは最早、現実とも演技とも判別不能である。おそらく、その双方であるだろう。エロス、暴力、脅威、哄笑、そして崩壊・・・。その荒涼とした身体の風景に何を読み取り、何を感じるのかは観客の自由だ。大橋の作品では、観客もまた現実と虚構の網目のなかに、自分自身の創造的な神経を研ぎ澄ますことを求められているのである。
(2008年2月)
「深淵の明晰」推薦文 [ abyss , dance ]
「深淵の明晰」京都公演は京都芸術センター舞台芸術賞2009のノミネート作品になりますが、ノミネートの選考をしていただいた、古後奈緒子(舞踊史・舞踊理論研究/批評)さんによる推薦文が公開されていましたので、紹介します。
ジャンル内の系譜づけによって保証される正当性を避けつつ、自己目的化した実験性に陥ることのない探求の姿勢と過去の成果が評価された。とりわけ、作品を貫く閉塞感の源となる身体や、複数のメディアにより構築される時間・空間は、今という時代において身体が被る現実と多様な関係を結びうる。加えて、舞踏という出自への姿勢、映像を用いた演出の手法等、方法論の点でも多角的な議論を開く可能性にも期待が寄せられる。
文章の内容はこれまで僕たちがプレス向けなどに書いているものと大差ないので、あまり新鮮味がない、というと失礼ですね。推薦文に負けないような作品を作りたいと思います。
山崎広太による大橋可也インタビュー [ dance ]
BAL (Body Arts Laboratory) の活動の一環として、山崎広太さんと印牧雅子さんによる大橋可也インタビューが公開されました。
今後の掲載予定も含め、そうそうたるアーティストのインタビュー集となっています。
BALの活動は今後も要注目です。大橋可也&ダンサーズとしても応援していきたいと思います。
「帝国会議」は「ひらく会議」に [ dance , empire_news ]
報告遅くなりましたが、「帝国会議」は無事終了しました。
多くの方々に立ち会っていただきました。本当にありがとうございました。
今回の企画は、一部で説明のためにシンポジウムという表現を使った場合もありましたが、名前のとおり、あくまで「会議」をおこなうことを目指しました。
「会議」であるということは、参加者が何らかの共通の目的を持ち集い、何らかの決議あるいは合意に達することが必要であると考えました。
では、今回の会議の目的とは。
コンテンポラリーダンスに関わるアーティスト自らが語ること、そしてそのための集まりを続けることです。
# ここではコンテンポラリーダンスの定義はひとまず措くことにします
その目的のために、僕が提案したことは、このような集まり(会議)を続けていくということです。
このことについては、参加者の合意は得られたと思います。
そして、決議したことは、続けていくために、会議の名称を決める、ということでした。
「ひらく会議」これがその会議の名称です。
したがって、「帝国会議」は記念すべき「ひらく会議」の第一回となりました。
「ひらく会議」の第二回は1/31-2/1におこなわれる「We Dance」で開催される予定です。
詳細は追って発表します。
この会議は毎回、主催も参加者も変化しつつ続けられる予定です。
出来れば月に一度は何らかの形で開催したいと思います。
会議ということで議事録を公開することも提案しましたが、そうすると参加する敷居が高くなってしまうのではないか、という意見もありました。
これは僕の理解ですが、決議事項だけ公開することとすれば、議事録の目的は達成できると思います。
そんなこんなで、「ひらく会議」が、ダンスに関わるアーティストにとって、そうでない人にとっても、ひらくこと、ひらかれていくことにつながればよいと願います。
協力を、参加を。
「帝国会議」あらため「ひらく会議」第一回
日時:2008/12/29 17:00-20:00
会場:森下スタジオAスタジオ
パネラー:伊藤キム(振付家・ダンサー/輝く未来)、遠田誠(振付家・ダンサー/まことクラヴ)、岩渕貞太(振付家・ダンサー)、山崎広太(振付家・ダンサー)、大橋可也
反抗の姿勢 [ dance ]
僕たちは何を見せればよいか、何を示せばよいか。
それはひと言で言うなら、反抗の姿勢というべきものだろう。
抗う姿勢を維持し続ける。僕たちが培ってきたものはそのための方法論だ。
何に対して、どのように抗うのか。それが作品の、活動のテーマとなる。
責任と課題 [ dance ]
2008/6/8に起きた秋葉原殺傷事件に僕たちは何の責任もないのだろうか。僕たちに出来ることはなかったのだろうか。
大橋可也&ダンサーズが取り組んできたこと、それはあの事件の加藤のように、現代の社会の中で心を身体を失ってしまった人たちに向けていたものだったと思う。
彼に届かなかったこと、それは悔いるべきことなのだ。
どうすれば届けられるのか。どうすれば彼の持ってたようなけっして無意味ではないエネルギーを救うことができるのか。
その課題に逃げないこと、立ち向かっていくこと。
オレたちの使命 [ dance ]
ダンス作品を作ったりしているのも、公演を打ったりしているのも、だってそうしたいからなのだが、あくまで個人的な内在的な衝動によるものなのだが、そこには明らかな理由というものが、いや使命というべきものがある。
すべての芸術がそうあるべきではない、確かにそうではあるだろう、だが、芸術の、1つの、そして極めて重要な役割は、現在の社会における支配的な価値観に対して異なる、オルタナティブな価値観を提示することである。
今の日本において、そのような役割を担っているものたちは何処にいるのか。いや、僕の知る限りはいない。
芸術に限ったことではない。何がオルタナティブなのか、誰が対抗勢力なのか、見えなくなってしまっている今このときこそ、オレたちの使命を果たすときではないのか。
見ることの意思 [ chain , dance ]
「明晰の鎖」公演で導入したチケット料金システムについて、fringeのトピックにて取り上げられました。取り上げていただきありがとうございます。
この機会に、僕たちの公演に料金を支払っていただくということについて、僕たちの考えを補足します。
芸術に支払うお金、僕たちの場合であれば公演の入場料金、というものは何かの対価に対して支払われるものではないと考えます。
それは、支払う側、僕たちの場合は観客と呼ばれる人々、の意思表示なのではないでしょうか。
観客の意思というものは千差万別だと思います。しかしながら、今回のチケット料金を設定するに当たっては、その意思を「作品に対して貢献すること」「作品を体験すること」「作品を必要とすること」と表すことで各料金との対応付けをおこなっています。それぞれは異なるレベルにあるものですし、独立しているものでもありません。また、観客の方々が、必ずしも僕たちが想定する意思を持って料金を支払っていただく必要もないと思います。
確固たる意思を持って僕たちの作品を見てほしい、いえ参加してほしい、そう僕たちは望みます。舞台芸術の作品は、観客が見ることによって初めて成立するものですから。
その意思を喚起させること、と同時に入場料金を支払うという経済行為の意味づけを問うこと、それが今回のチケット料金システムに込められた意図なのです。
芸術家個人とはいったい誰か [ dance ]
大橋可也&ダンサーズは2007年よりセゾン文化財団より「芸術創造活動」のプログラムにて年間300万円の助成を受けている。それ自体は僕たちにとって、もちろんあなたたちにとってもね、よいことであるのは間違いない。
そのことは措くとして、来年度からセゾン文化財団の助成方針が変更になり、芸術団体に対しての支援から、芸術家個人に対しての支援に変更になったので、そのことに関連したことを書くとしよう。
プログラムガイドライン 芸術家への直接支援
今の日本では、ダンス、演劇だってそうだろう、振付家、演出家、劇作家、肩書きは何でもいい、そんな連中が中心となったプロデュース、ユニット形式の活動が中心となっていて、団体を維持して活動していくケースは減るいっぽうであると言っていいだろう。団体といっても助成金をもらうための名ばかりのものもあるよね。件のセゾン文化財団から助成金を受けている団体の中にも。
そういう現状を鑑みれば、個人を対象にした支援にシフトすることは間違ってはいないだろう。果たしてそうだろうか。
よくよく考えてみなくてはいけない。芸術家個人とは誰か、ということを。その個人が存在するとして彼、あるいは彼女の活動に助成金というものが必要なのだろうか。いや、必要ではない。
芸術家とは活動の経済的な規模に関わらず、芸術家なのであって、経済的な規模が小さければそれに見合った活動をするのだ。その活動を維持するために助成が必要な芸術家など存在してはいけない。そうだよ、金なんていらないのさ、芸術家にはね。
ならば。芸術団体とは何か。芸術が社会に存在するための基盤を構築するための拠点となるものである。そこにはダンサー、役者、スタッフたちが集い、それ自体が社会の一部を形成するものなのだから。そして、彼らを通じて社会全体と関わりを持とうとするものだから。
その基盤を維持、発展させていくためには経済的な支援が、助成が必要なのだ。その基盤が社会に根付くまでは。そうは思わないかい。
セゾン文化財団には再来年度から助成方針を再考していただきたい。もちろんこの意見を直接伝える機会を持つことにする。
旅、あるいは移動について [ dance ]
いつの頃からか旅ということを意識するようになった。僕はもともと旅に出ることなんて興味は無かった。まあ、言ってみれば引きこもりだしね。今だって出かけることは嫌い。そうなのだが。
今ここにいることだって旅の途中ではないのだろうか、そんな気がしてくるようになった。多分、そんな思いと関係がないわけではないだろう、昨年の『明晰さは目の前の一点過ぎない。』は「イクストランへの旅」をテキストに使っていたし、その次の作品は『Journey Beyond the Clarity』と名づけたのだった。
「モーション(移動)はエモーション(感情)を生む」とはヴィム・ヴェンダースの言葉らしい。僕はこの言葉をリュミエールだかで目にしていて、最近までヴェンダースの言葉ではないと思っていたのだが、稽古場ではずいぶん使わせてもらっている。そう、移動は物理的な距離とは関係ないのであって、むしろ感情を生むために必要な体験なのではないだろうか。
僕は、僕たちは、とどまること、簡単に言ってしまえば劇場に、そのシステムに在り続けるいうことなのだが、そのことによって外界との境界線を切り崩そうとしてきた。その方法は間違っていないと思うし、もちろん意図してのこと。もう境界線を軽く越えてもいい時期かもしれない。
そろそろ旅に出ようか。最初の漂白地はけっして遠い地ではないだろうけれども。
ダンス蛇の穴第一期 [ dance , snakepit ]
ようやくダンス蛇の穴第一期のプログラムが決まりました。
今回は、ダンスクリティーク、音響レクチャー/ワークショップ、創作ワークショップのラインアップで、2007/10/11から2008/1/13まで合計8回おこないます。
mixiダンス蛇の穴コミュ
※最新情報は随時更新します。
「関係者全員参加!ダンスクリティーク」司会:木村覚
「牛の耳 ダンスをもって音をたちきれ」牛川紀政音響レクチャー/ワークショップ
「出演者と観客による集団創作は可能か?」企画、進行:垣内友香里
会場:
森下スタジオ(2007年11-12月はBスタジオ、2008年1月はAスタジオ)
東京都江東区森下3-5-6
地下鉄都営新宿線、都営大江戸線「森下駅」 A6出口徒歩5分

時間;18:30-21:30
料金:1000円(当日のみ、ドリンク代込み)
助成:財団法人セゾン文化財団
企画制作、主催:大橋可也&ダンサーズ
問い合わせ:
大橋可也&ダンサーズ
mail: office@dancehardcore.com
tel: 03-5789-9892
fax: 03-5789-9893
tel: 070-5218-5251(当日のみ)
「ダンス蛇の穴」について
ダンスは必要。世の人々にとって、ダンスがもっと意味あるものであればよいと思う。そのためには、僕たち、ダンスを作り出すものたちが、ダンスの意味を高めていかなくてはいけない。言葉を持つことも欠かせないプロセスだ。
ダンス蛇の穴は、来たるべきダンス作家を、スタッフを、制作者を、批評家を、観客を、ダンスそのものを産み出すための道場として機能していくことを目指していきます。
蛇の穴の由来は、ビリー・ライレージムより。
「明晰の鎖」ワークインプログレス上演にあたって [ chain , dance ]
2008/2/9-11に吉祥寺シアターで初演をおこなう大橋可也&ダンサーズ新作「明晰の鎖」のワークインプログレス公演を2回に分けて実施します。
大橋可也&ダンサーズにとって、観客とは舞台上の出来事を受け止める対象ではなく、出来事を成立させるための登場人物であるといえます。
今回のワークインプログレスでは「明晰の鎖」の創作過程にある出来事を公開します。来るべき作品の登場人物になっていただける方をお待ちしています。
「明晰の鎖」チケットについて [ chain , dance ]
大橋可也&ダンサーズ新作公演「明晰の鎖」のチケットについての説明です。
料金システムが分かりづらいとは思いますが、これも僕たちの作品の意思表示の1つと考えてください。
2007/12/21更新 見ることの意思について追記しました。
格差社会を芸術にとっても重要な課題であると考える大橋可也&ダンサーズは、3種類の料金設定によってチケットを提供させていただきます。
チケットA:¥20,000 お金に余裕があるので作品に貢献したい!
チケットB:¥5,000 ともかく作品を体験したい!
チケットC:¥0 お金はないが自分には作品を見る必要がある!
※全席指定、前売・当日とも同一料金
発売開始:2007/11/17
料金の差は席の違いを表すものではありません。
チケットAにはお土産が付きます。
チケットCは枚数に限りがあります。チケットCの当日発売はありません。
詳細はお問い合わせください。
【チケット購入方法】
チケットA, Bをご希望される方⇒

・チケットはご予約後10日以内に、お近くのセブン-イレブンでお支払い/お受け取りください。
・観劇ポータルサイト「カンフェティ」への会員登録(無料)が必要となります。
登録をすると、他劇団のチケットにも使える共通ポイントが貯まります(初回99ポイント+購入価格の1%)。
・席を選んでご予約できます。
・予約直後からセブン-イレブンで受け取り可能です。
※ご注意:当システムは 「Windows VISTA」 に対応しておりません。大変申し訳御座いませんが Microsoft Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP または MacOS 9/10 をご利用ください。
チケットぴあ
0570-02-9999(Pコード381-130)
チケットCをご希望される方⇒
下記申し込み先まで以下の内容をメール、FAXまたは郵送で送付してください。
・名前/住所/メールアドレス/電話番号
・私は何故に大橋可也&ダンサーズの作品を無料で見る必要があるか(書式自由)
〒150-0012
東京都渋谷区広尾1-10-5日興パレス広尾プラザ604
大橋可也&ダンサーズチケット申込み係
fax:03-5789-9893
mail:office@dancehardcore.com
【問い合わせ】
大橋可也&ダンサーズ
tel:03-5789-9892
fax:03-5789-9893
mail:office@dancehardcore.com
就職氷河期 [ chain , dance ]
「明晰の鎖」のための覚え書き。
僕はバブル世代ど真ん中であり、まともに就職はしなくて最初に就職した会社も1年で辞めてしまったけれど、再就職してからは、たいへんなこともあったが何とか充実した職を続けていけていると思う。それは主に自分の努力によると思っていた。もちろん、タイミングに恵まれていたのも事実なのだが。
だから、就職に関する問題、フリーター、ニートたちにしても、それは彼ら自身の問題なのだと思って、ほとんど関心がなかったといってよい。しかし、明らかな事実として就職氷河期と呼ばれる時期があり、その時期に就職しようとした人たちの問題は今後の日本にとって大きな社会問題なのだ、ということにようやく最近気がついた。実際は僕自身もこの時期に再就職をしているので、無関係ではなかったのだが、そのことは措くとする。
彼らが本来技能を身に着けるべき時期に、その機会を逸してしまったこと、それは今の日本ではある程度の年齢に達した人が技能を身に着ける機会を持つことが困難であることを考えれば、これから何十年にも渡ってぽっかりと技術、技能を持たない世代が存在し続けることになるのだろうか。日本は技術立国ではなかったか。そのこと自体が幻想なのかも知れないが。
ここは就職氷河期について議論すべき場所ではない。では、どうしてそんなことを書いているかというと、僕たち、氷河期世代に先立つ世代のものが何をすべきか、考えなくてはいけないと思うからである。
僕自身はアーティストだから、作品によって、作品を作る姿勢によって、あらゆる問題に取り組んでいく。この問題についても同じことだ。
現行ダンサーズの平均年齢は29.8才、氷河期世代ど真ん中だ。彼らに関心を持とうとしたこと、それが今の僕の問題意識につながっている。関心を持つこと、何より大事なこと。
バウムクーヘン [ chain , dance ]
バームクーヘンではないらしい。「明晰の鎖」のための覚え書き。
今回の作品の1つのパートはバウムクーヘン同様に構成されていて、その制作方法もそれから影響を受けている。
これはどういうことかというと、個々の振りの層を同心円状に重ねていきながら1つの芯を持つ振付の固まりを作ってから、それを輪切りにして食するということ。って分かりづらいな。まあ、覚え書きなので。
食卓に並べるときには、輪切りにした切れ端をずらしながら重ねていき、それぞれに異なった味付けを施していく。もっとも食べる直前に一度ミキサーにかけてしまおうと思っているけれど。
状態遷移 [ dance ]
ダンサーは常に1つの状態(ステート)にあります。ある状態から別の状態に移ること、すなわち状態遷移が、振付に動きを、流れを与えます。つまり、ダンサーの動きとは状態遷移のプロセスに他なりません。
遷移の契機となるもの、それは外部からの刺激であるときもあれば、内的な感情の変化であるときもあります。
振付家とダンサーは、現在の状態、遷移の契機について共通認識を持つ必要がありますし、その共通認識が振付を表す言葉になるのです。
ダンスの快楽について [ dance ]
「土と塩」公演まで、あと1週間あまりとなりました。
今回の作品は、ある意味では大橋可也&ダンサーズ史上に残る意欲作だといえます。
なぜならば、今回の作品では、爆音、ストロボ、極端な身体のフォルムといった、ある種の分かりやすさを持った形象は登場しません。おなじみといってもいい、セックス、暴力のイメージも、少なくとも表面的にはですが、無縁の作品です。
では、見どころがまるでない作品になってしまうのでしょうか。
ある人々にとってはそうかもしれません。
しかしながら、僕は毎回の稽古を楽しんでいます。これだけ振付のディティールにこだわることの出来たことは今までありませんでした。ぎりぎりまでこだわるつもりです。
そのこだわりが、多くの人にとっても快楽と感じられるのだろうか。
その問いを投げかける作品になるでしょう。
間、ま [ dance ]
大橋可也の振付の外面的な特徴を一言で言い表すとするなら、それは「間」です。
では、間はどのように生まれるのでしょうか。
それはダンサーの内的体験に基づいています。ダンサーが感じること、思うことが時間的、空間的な間を生み出します。ですから、大橋可也の振付にスコアと呼べるものがあるとすれば、それはダンサーの内的体験に他ならないのです。
このスコアは土方巽が残した、弟子達が記述したといった方が正確でしょうが、暗黒舞踏の舞踏譜と近しいものです。そして、大橋可也はその振付を舞踏譜の豊かな世界に近づけたいと思うものでもあります。
内的体験は外的世界の反映である、と言うことも出来ます。
身体を器にし森羅万象をそこに映し出すこと。
舞踏の方法論を端的に言い表すなら、語弊はあるかもしれません、このような表現になるでしょう。
これは大橋可也の振付にも当てはまります。森羅万象というと自然というか人間が関与しないものを想像しがちですが、人間社会の出来事も森羅万象の1つであるに違いはありません。
僕たちが今生きている社会の出来事、日常といってもいい、を内的体験に反映させる。
これが大橋可也がやっていることです。
そこで生まれる間、さあそれは日常の間とどう違うのでしょうか。
この違いに、僕たちは、振付の、ダンスの楽しみを見出すのです。
9(nine)マインドマップ [ dance , nine ]
2007/6/9に多摩美術大学で國吉和子さんとおこなった9(nine)に関するレクチャーにて使用したマインドマップです。
http://dancehardcore.com/nine/9(nine)_lecture_20070609.html
9(nine)の制作過程において僕が重要と思う項目を列挙しています。
インストラクション20070602 [ dance , nine ]
昨日(2007/6/2)の稽古に使用した9(nine)後半振付のためのインストラクション(動作命令)。
しかし、これは振付ではないしスコアでもありません。
通常は稽古に先立ってインストラクションをテキスト化しておくことはなく、稽古を進めながら口頭でインストラクションを構成していきます。昨日、テキスト化したのはあくまで作業効率のためですが、テキストをダンサーに渡すのではなく、やはり口頭で伝えています。
ごめんなさい × 6
キック × 3
左手 × 19
首振り × 2
(叫び)
左手 × 2
首振り × 6
ごめんなさい × 3
左手 × 6
立ちくらみ途中まで × 2
左手
左足すべる
立つ
振り向く
左足すべる
グニャリ
ゲロから立ち上がる
左足すべる
グニャリ
ゲロから上体起こすまで
右回り × 5
雑巾から立ち上がる
雑巾繰り返し
左足すべる途中まで
立つ
プルプル
横移動
ゲロ床まで
立つ
ふらー
キック繰り返し
振り向く
ごめんなさい
首振り × 8
矢沢さん × 3
対立についてのメモ [ dance , nine ]
こんな感じ。
モノクロとカラー
匿名と自分
同質と異質
指示と内的動機付け
全体主義と個人の意思
一神教と多神教
男と女
必要なものと必要のないもの
振付家とダンサー
学校は嫌い [ dance ]
近々、大学で公演をやろうとしていて、もちろん大学側にもお世話になっているし感謝もしているのだが。
なんで大学って存在するのか分からないのです。特に芸術系の大学は。理系の大学だけは必要だと思いますよ。
物心ついた頃から学校は嫌いでした。といっても反抗する気力もないし、反抗する対象もない、先生が学校という制度を代表しているわけではない、ので普通に学校には行ってました。それも成績は良かったりしたので、そこそこ優等生と思われていたのでした。
特に嫌いなのは休み時間。授業はいいんですよ。聞いても聞かなくても時間は過ぎていくので。なんで休み時間に遊んだりすることまで強制されなくてはいけないのでしょう。
思い出話はここまでにして。
教育は必要である。それは芸術についても同じだ。しかしながら、その場が学校である必要はないのではないか。学びたいときに学ぶことが出来る環境、それがすぐここにあるべきだ。図書館もすばらしい。すべての人にとって必要なものだ。しかし、それが閉ざされた空間にあってはいけない。
ダンスも教育である。僕もアーティストであると同時に教育者として生きたいと思う。
その場を作っていきたい。学校という制度に閉じこもることなく。
突破する [ dance ]
何を為そうとするにも目的や動機付けというものがあるのだが、9(nine)にももちろん目的がある。それは2つのブレークスルーだ。
1. アーティストとして
大橋可也は閉ざされたシステムの中で作品を作ってきた。これからもそうだろう。
これまでの作品中でのダンサー達は、ダンス経験の長い者もいるのだが、そのダンサーとしての特性をある意味消していきながら、参加していたと思う。
完成されたダンサー、それも自らの振付法を持つダンサー、に振付することは大橋可也の振付、作品にどのような影響を与えるのか。それが今回の挑戦である。
なおかつ、ソロであること。関係性から始めていた振付の大きな転機となるか。
東野祥子も自分のシステムで作品を作ってきた。即興セッションは数多くおこなっている彼女でも、他者の振付、演出の作品に身を委ねることはなかったそうだ。
他者の振付で、しかもソロとして踊ることは彼女にとっても大きな挑戦だろう。
2人のアーティストが自身の壁をブレークスルーすること。
2. ダンスシーンに対して
日本のダンスシーンは閉塞的だと思う。そのこと自体は必ずしも悪いことではない。観客も少なくて構わないと思う。その中身が、つまりは作品が、作家が、作家と観客の姿勢が、充実していれば。
作家も作品も使い回し、消費されて終わっているのではないか。
ダンサー、振付家ののコラボレーションもよくある。しかし、それらの多くは制作主導であり一過性かつ作家の意図が不明確なものだ。
作家が自らの意図でシーンを作らないといけない。それは僕が常に主張していることである。
ダンスシーンの構造をブレークスルーすること。
芸術家とは何か [ dance ]
僕は自分自身を芸術家だと信じている。では、芸術家とは何か。
知識人とは亡命者にして周辺的存在であり、またアマチュアであり、さらには権力に対して真実を語ろうとする言葉の使い手である。
エドワード・W・サイード「知識人とは何か」より
ここでいう知識人を芸術家に、言葉を作品に置き換えるなら、僕の考える芸術家の定義となるだろう。
コンセプト [ dance ]
身体は何も表現しない。
とはいえ、ダンス作品にはテーマやコンセプトといわれるものがあり、僕もその存在の必要性を否定しない。
ダンス作品におけるコンセプトは何を意味するのか。
それは身体の存在意義を明確にするためのものだ。コンテンポラリーダンスと呼ばれる僕たちのダンスであれば、現代社会において身体がどのように存在しうるのか、ダンスはどのように成立するのか、その問題に1つの解決方法を提示するのがコンセプトの役割である。
身体表現は存在しない [ dance ]
僕たちのやっていることは「身体表現」とカテゴライズされることもあり、僕も人と会話をするときには、その使用について否定したりはしないのだが、まあ大人だからね。
身体表現とは何を意味するのか。身体が何かを表現する、ということが有り得るのか。そんなことは有り得ない。身体は何ものの表現しない。身体は、そこにいかなる動きが形容が付け加わろうとも、身体そのものを提示するだけなのだ。
身体表現は存在しない。
身体表現という言葉が存在する背景には、表現することが芸術である、という信仰があり、人間にとって原初的な活動であるダンスを芸術に位置づけようとするために、身体の外にその存在価値を求めようとする志向がある。要するに、頭で考えたことを表現することが偉い、という価値観があるのだ。
そんな信仰も価値観も僕たちには必要ない。
言葉の誤用を改めることも僕たちの使命である。
9(nine) 多摩美術大学レクチャーに関連して [ dance , nine ]
「9(nine)」多摩美術大学新図書館公演に先立つレクチャー(2007/5/19, 2007/6/9)の講師をつとめていただく木村覚氏、國吉和子氏から、今回のイベントに向けての文章です。
新作の稽古+代表作と最近作をフルヴァージョンで見ること--それは、現在注目の作家・大橋可也の芸術観や方法論に迫るチャンスであるばかりか、いまの日本で起きているダンス・ムーヴメントの最も濃密な部分に触れる絶好の機会となるに違いない。なぜ、いまこうしたアプローチを「ダンス」と呼ぶのか?その発端である60年代のアメリカに登場したポスト・モダンダンスと照らし合わせながら、ダンス系アートの現在と過去を解明してゆく。(木村覚)
私は大橋可也を舞踏家だと思っていた。その後、彼は競輪の選手なんだ、と思いなおし、今は演出家だと確信している。演出家は普通観客の前に姿を現さない。が、大橋はいつも会場のどこかで必ず観客を見ている。さりげなく会場に紛れ込んでいる様子は、まるで何食わぬ顔で犯罪現場に戻ってきた下手人のようだ。この度は図書館エントランスの不安な傾斜の上だ。彼の遠近法はダイナミックに歪むだろう。(國吉和子)
【レクチャー講師プロフィール】
木村覚(きむら・さとる)
1971年、千葉県生まれ。美学研究者として多摩美術大学、国士舘大学、専修大学で非常勤講師を務める。その一方で、ダンスを中心としたシアターをめぐる批評活動を『美術手帖』やwonderland(web)等の誌上で行う。2007年2月に横浜・急な坂スタジオで行った8回シリーズ『超詳解!20世紀ダンス入門』の構成・司会・講師を担当するなど、今年はダンス史を解明するレクチャーに精力的に取り組んでいる。
Sato Site on the Web Side
イベント告知
國吉和子(くによし・かずこ)
舞踊評論、研究。現在、早稲田大学、多摩美術大学非常勤講師。
著書『夢の衣裳、記憶の壺――舞踊とモダニズム』(新書館)
市川雅遺稿集『見ることとの距離 ダンスの軌跡1962-1996』(新書館)を編集。
ダンス蛇の穴(仮称) [ dance ]
最近、更新が滞っている。
作品制作の時期になると、それ以外のことについて考える余裕がなくなる。いや、実際には余裕がないわけではなくて、甘えているのだという気もする。
1つ考えていることを書く。
「ダンス蛇の穴(仮称)」というものを考えている。
大橋可也および大橋可也&ダンサーズの活動は、もっとエッジに向かうべきだと思う。広く受け入れられる必要はない。出演者、観客もコアに閉じていく、その純度を高めていくことが重要だと思う。
しかし、僕たちが考えている、社会にとって必要なダンス、ということを伝えていくためには、僕たちの活動だけでは足りない。活動の機会も少なすぎるし、単純に作品の好みということもあって、伝えたい人たちに本当に伝えられているか、という問題がある。
ダンスは必要なものだと思う。
そのことを訴え、考えていくための場を作りたい。その場では、僕たちが中心にいる必要はない。
今やっているレクチャー(第1回、第2回)もその方向性にあるものだ。
今後、レクチャーだけでなく、ダンスについて考え、次のダンスを創造していく場を作っていく。ワークショップ、ディスカッションなどを含め、出来れば毎週開催していきたい。
どのような形態であれ、アーティストがその中心にいることが重要だ。
2007年8月にはより具体的な内容を伝えることができると思う。
「蛇の穴」という名称は単に僕の好みでしかないので、よい名称があれば教えてください。
今、関心のあること [ dance ]
久しぶりの更新になりました。年度の変わり目はなんだかんだ落ち着きません。
2007年度より、セゾン文化財団の年間助成を受けることになりました。詳細はセゾン文化財団の報告資料(PDF)を参照してください。
それはもちろん、僕たちにとって、社会全体にとって、いいことです。
皆さんおめでとう。
それはさておき、今回の助成を申請するにあたり、エッセイというものを提出したのですが、せっかく書いた文章なので、ここに転載しておきます。
題は「今、関心のあること」
「今、関心のあること」大橋可也(大橋可也&ダンサーズ主宰・振付家)
はじめに
正直なところ、世の中の出来事にはほとんど関心がない。僕が関心を持つのは、自分のことだ。それも詰まるところは「自分とは何か」っていう問い、だけなのだよね。その問いは物心ついたころから持ち続けている。だから、ほとんど精神的には成長していないともいえるのだが。しかし、そんな問いに答えなどない、たぶん、のであって、今は答えに至るための方法に関心を持つことにしている。その方法は「正しく生きる、生きたい」ということ。これもまた漠然としているな。じゃあ、正しいって何か、ということから始めないと。ヨガの八枝則で最初に来るのは、ヤマ。ヤマは他者に対して守るべき行動パターンを定義していて、それらは、暴力を振るわない、盗まない、正直になる、性的欲求に溺れない、物質欲にとらわれない、の5つである。うん、これらは正しそう。逆にいったら、僕たちは、暴力を振るうこと、盗むこと、嘘をつくこと、性的欲求、物質欲、が好きなわけだ。この意見にもアイ・アグリーだ。では、僕たちが最初に好きなこと、暴力を振るう、に興味を持つのは至極リーズナブルな流れだね。ということで、僕の活動と暴力の関係を考察してみることにしよう。
暴力
多くの人々が間違って認識しているように、ひょっとしたら僕の認識が間違っているのかも知れないが、暴力とは、殴る、蹴る、などの物質的攻撃のことを指すのではない。暴力とは、ある種の関係性が成立している状態のことである。その関係性とは、強者と弱者が峻別され、弱者の意思によっては変えることができない、という状況である。そして、暴力的行為とは、強者を強者たらしめ、弱者を弱者たらしめるためにおこなわれる行為のことを指す。だから、平均的な体格の女性が平均的な体格の男性を殴ったとしても、それは暴力ではない。肉体的に優位に立つ男性が下位にある女性を殴ったとき、それは暴力的行為であり、彼らの関係性は暴力と呼ばれるのである。
連鎖
暴力は普遍的に存在している。とりわけ、現在の日本、に限らないだろうが、において重要なのは、弱者と更なる弱者の間の暴力である。夫から妻、妻から子供、子供から別の子供と、連鎖は続いている。つながりつづけるということ、それ自身が暴力の持つ特性といえるのかもしれない。
身体
連鎖する暴力は必ずしも身体を必要としない。しかしながら、暴力の存在を開示するもの、それは身体である。傷痕。更にいえば、暴力を克服するための手掛かりになるのも身体であろう。連鎖から生まれる傷が、連鎖の内側からブレーキをかけるのだ。現代に生きる僕たちは、日常生活において身体を自覚することが少なくなっている。自覚が無くても生きるに不自由はしない。せいぜい、病気になったとき、怪我をしたときぐらいしか自覚する機会、必要がないのだ。身体への意識への欠如は暴力を暗黙のうちに肯定している。傷跡を見過ごしているのだ。身体への意識を取り戻すこと、そこに鍵がある。
ダンス
身体を使って僕は自らの活動をおこなっている。そして、その活動を「ダンス」と呼ぶ。ダンスと名乗っていることの動機付けについてはここでは語らないが。ダンスを一言で言い表すなら、身体の関係性に他ならない。ここでいう身体は、自分自身のものである場合もあれば、他者のものである場合もある。ダンスは特定の身体の優位性を証明するものではない。身体の関係性を変容させ、価値観を作り直していくものだ。だからこそ、ダンスは、暴力の連鎖を止める手段に成り得るのではないか。
振付
ダンスは振付からなる。そして、振付は僕のしごとである。では、振付とは。身体の境界線を定義づけるもの、それが振付である。振付によって、自分自身の身体と他者の身体の境界線が描かれるのである。振付の手法とは、その境界線を描く道具立てのことである。どこから、どうやって境界線を描くのか。ここで、既存の社会の価値観、個人の人格から出発してはいけない。それでは、同じ境界線しか描くことはできない。感情、感覚を分解し、ブラシのエッジを際立たせることによって、新しいラインを描いていく。ゆらぎ、ぶれ、ぼかしも必要だ。身体の境界線は常に明瞭に描かれているわけではない。その境界線によって、暴力の連鎖をせきとめ、迂回させたい。
結び
世の人々のために何か意味あることをすること、それが「正しく生きる」ことなのだろう。だから、僕は自分がやっていることの意味づけを探す。だから、ダンスって何、という問いかけについても、ダンスと呼ばれるものが、どのように意味があるか、という視点から考えなくてはいけない。そう、意味がないものはダンスって呼ばないのではないの。僕はダンスと、ダンスによって正しく生きたい。それが、今、関心を持っていることだし、これからも関心を持ち続けたいことだと思う。
ある稽古の方法 [ dance ]
先週土曜日は木村覚さんを招いてのレクチャーを開催した。
内容としては「ジャドソンダンスシアター」にフォーカスしたもので、それ自体興味深いものだったが、そのことについては改めて書くことにしたい。
ここでは、なぜ僕たちの稽古場でレクチャーなのか、ということについて書く。
ここのところ、ダンスについての言葉が足りない、ということをあらゆる場所で言っている。足りないのは、見る側、観客、批評家にとってでもあり、作る側、ダンサー、振付家にとってでもである。だから、見る側も作る側の関係が、特定の作品が面白い、面白くないという程度の感想の交換に終わっているのだ。
# もちろん、面白いと思う、感じることは、ダンスを見る、作る上で欠かせない動機付けであることは大前提として
僕たちはダンスを、自分たちがおこなっていることを意味あるものにしていきたい。そのためには、僕たちが何を目指しているのか、ある作品を作るとしたら、何を課題とするのか、明確でなくてはいけない。その上で、特定の作品が達成したこと、達成できていないことを、作品と作家の評価とすることができるのだろう。
確かな言葉を持つこと、それはダンスの稽古である。
そして、稽古の方法の1つが今回のレクチャーなのだ。
【レクチャーに興味をお持ちの方へ】
原則的には非公開ですが、問い合わせいただければ詳細についてお知らせします。
レクチャーの対象者はダンサー、振付家、あるいはそれを目指す人、およびダンスの制作現場に関わっている人です。
コンテンポラリーダンスマッシュアップポータル [ dance ]
Web2.0の時代だというのに、コンテンポラリーダンスの上演機会も増えてきているというのに、いまだにインターネット上でコンテンポラリーダンスの公演、アーティスト情報をまとめて参照できるポータルサイトがない。JCDNのサイトとダンスリザーブはその種の役割を持っているが、情報公開には会員になる必要があったりとかの敷居があり、検索などの利便性にも欠けている。
じゃあ、新たにポータルサイトを作って情報を集約すればいいかというと、そうではない。新たに作ったところで情報をそこに登録しなければならないし、サイトを閲覧する人を誘導していく活動も必要になる。そんなコストを掛けられるほど僕たちは裕福じゃない。
実のところ、必要な情報は既にアーティストや劇場のホームページかブログに存在している。
そう、マッシュアップですよ。
世の中にはPlaggerとかあるらしい。チャレンジしてみるか。
コンテンポラリーダンスマッシュアップポータルの概念図を書いてみた。
あくまでアーティストが主体であるというのが肝心。そこに観客などのステークホルダーがその立場から関わりを持つことが出来るようにする。
本当はこのエントリを書く前にこのシステムのアルファ版ぐらいは作ろうと思っていたのだけど、1時間ぐらいで断念しました。自分の技術力と根気の無さに少し落胆を覚えています。
このエントリもアップするまでに2週間ぐらいかかってしまった。
どなたか協力してくれると嬉しいです。欲しいのは以下のような人材です。
1. コーディングスキル(Perlかな)のある人
2. 1は無くても、自由に使える時間のある人
3. 1も2も無くても、アイデアのある人
4. 1も2も3も無くても、ダンスに関わっているか興味を持っている人
このシステムは繰り返し書いているアーティストが作るメディアの実現例の1つです。
その存在が害でしかない芸術作品もある、という現実にアーティストはどう直面するべきか [ dance ]
僕はアーティストなので、芸術の可能性を信じている。すべての芸術作品は存在意義があると思うし、そう思いたい。
しかしながら、その存在意義を認めたくない作品もあるのだ。
劇団解体社の公演「要塞にて」を観にいった。理由はある演劇批評家の方に薦められたからである。
僕の作品と解体社の作品には親和性がある、それは認めよう。いや向こうのほうが有名なわけで、そんな偉そうな態度はとりませんよ。喩えていただけれるだけで喜ぶべきか。
いえいえ、作風だとか作品の要素だとかはどうでもいい話。
芸術だからといってやっていいことと悪いことがあるでしょう。
「要塞にて」ではビデオによるテロップが流れる。その中の一部分は従軍慰安婦に関するものだ。その文章は従軍慰安婦は日本政府が公式に強制的におこなった制度だと訴えている。
# 文言は正確ではない
これは正しくない。安部首相が最近発言したとおり、強制があったという証拠はない、のが歴史的事実だ。
僕は従軍慰安婦問題について語りたいわけではない。
彼らが、解体社がその問題を扱うやり方について異議を唱えたいだけだ。
なぜ、その問題を作品で使うのか。
理由は簡単だろう。物議をかもす問題を取り上げることで作品に緊張感を加えたいだけだ。
もし、作品によって社会問題を世にアピールしたいのであれば、スピルバークが、イーストウッドがそうしているように、エンターテインメントとしてより多くの人々に問題を知ってもらうようにする方法がある。あるいは、その問題を加工することなく、取り上げるべきだろう。
1行、2行のテロップで何が伝わるというのか。何が理解できるというのか。
問題に対する誤解を増幅させるだけでしかない。しかも限られた観客層の中で。
少なくともこれだけは言える。
解体社の姿勢は従軍慰安婦問題に真摯に関わっているすべての人々に対する冒涜である。
そして、すべての芸術に対する冒涜である。
アーティストである僕はその姿勢をけっして許したくない。
なぜアーティストは貧乏なのか? [ dance ]
まだ読み終わっていませんが、お薦めします。
著者はオランダ人のアーティストで、かつ経済学者であるとのこと。
本の内容もヨーロッパにおける芸術事情に基づいている。
なのだが、日本の舞台芸術関係者が読んだとしても、思い当たること100連発でしょう。
芸術には神話がある。
- 芸術は神聖である。
- 芸術を通じてアーティストと芸術消費者は神聖な世界とかかわる。
- 芸術は縁遠くて余計なものである。
- 芸術は贈与である。
- アーティストには天賦の才がある。
- 芸術は一般の利益に奉仕する。
- 芸術は人々のためになる。
- アーティストは自律的である。すわなち、他の職業は自律的ではない。
- 芸術には表現の自由がある。
- 芸術作品は本物であり、アーティストはその唯一の創造者である。他の職業にはそのような本物らしさはない。
- 本物の作品創造は果てしない個人的満足を与える。
- アーティストは無私で芸術に奉仕する。
- アーティストはひたすら内的に動機づけられている。
- 金銭と商取引は芸術の価値を貶める。
- コストと需要から解放されたときにのみ、芸術的な特質が生まれる。
- アーティストは耐えなければならない。
- 才能は生まれつきのもの、あるいは神が授けたものである。
- 誰もが才能に恵まれるチャンスを平等に持っている。
- 芸術的才能はそのキャリアの終盤になって初めて現れる。
- ずば抜けた才能は稀なので、アーティストを蓄えた巨大なプールがあって初めて、ごくわずかの飛び抜けた才能あるアーティストを社会に供給することができる。
- 成功は才能ともっぱら献身にかかっている。
- 芸術は自由である。他の職業に厳然としてある障壁はない。
- 成功したアーティストには独学の者もいる。
- 天賦の才、献身、平等なチャンスが芸術にはある。すなわち、最高の者が勝ち残る。
- 最高の者が勝つために、芸術は民主的で公正である。
- 数人のアーティストが稼ぐ高額な収入は正当なものである。
その神話ゆえに芸術が理解されない、アーティスト自身が勘違いをしてしまうことがあるのだろう。
僕たちがやっているコンテンポラリーダンスは文字通り、今僕たちが住んでいる社会の反映である。だから、僕たちがどうやって生きているのか、金を得ているのか、は作品性、作家性とけっして無縁ではない。
にもかかわらず、ダンスを取り巻く経済事情も、アーティスト、制作者以外には知られないままだ。
その状況でいいとは思わない。
金と芸術について考える機会を、アーティストから、作りたい。
まずは「金と芸術」の読書会でもやろうか。
無感動という体験から目を背けない [ dance ]
作品の内容については書かない、と書いたのだが、ニブロール「no direction。」についての感想を書いておく。
コンテンポラリーダンスという狭い業界の中で、他のアーティストの作品に対して否定的な意見を表明することの意味に疑問を感じないわけではない。足を引っ張り合うっていうことに。だが、彼らは評価を得ている、観客が来ている、助成金をもらっているカンパニーなのだから、否定的な意見を表すことにも意味はあるだろう。
# これまでにもずいぶん否定的な表現を使っているように思えるかも知れませんが、それは僕の表現が稚拙なせいであって、共感できるアーティスト、作品しか取り上げていないつもりです。
全体的な印象
いい大人がその財力を使って高校全国演劇大会に無理やりエントリーしてしまった。
その耐え難いダサさ
僕が以前にニブロールの作品を見たのは1999年だけである。そのころから矢内原美邦が才能ある振付家であること、その大胆さと情熱については理解していたつもりだ。と同時に、その作品世界、とその世界を構成する要素のダサさは当時から全開であった。
おそらくは、そのダサさが親近感を生んでいたのではないかと思う。確かに僕もそのような感情を持ったのは事実なのだ。
で、今回の作品ではどうだったか。そのダサさが遥かにグレードアップ、スケールアップしていたのだった。
やっていること自体は変わっていないと思う。だが、ここまでダサさが圧倒的だともうこちらの感覚が麻痺してしまう。何も感じる、考える気力が失われてしまう。
それが狙いだとすれば、なんと空虚な体験なのか、観客である僕たちにとって。
そのモチベーションの不思議さ
多分、衣装なんかは、あえてそのダサさを前面に出しているような気がする。音楽についてもそう。粗製乱造を狙っているというか。ただし、時折、審美的に良いと感じられるシーケンスがあったりするので、乱造ぶりがぼやけてしまい、かえって作品全体のダサさを強調することになっているのだが。
しかし、映像とかセリフとか振りは、どこからそれらを作ろうという動機付けが生まれるのか理解できない。ましてや、その動機付けを公演を上演するまで維持するということなど。
映像についていえば、今や普通にビデオカメラで撮ってPCを通せば見栄えのあるものが出来てしまうわけで、よほどの批評性を持たないと、映像作家として作品を作ることに耐えられないのではないかと想像してしまう。
みんな、もっと生産的なことに労力を使いませんか。
その驚くべき寛容さ
で、東京公演を見た結果は、嫌いな要素はいっぱいあるんだけど (上述の通りテーマにはあまり共感していないし、音楽もコンテンポラリーじゃないと思う) 全体としては結構好きだという感想を持ちました。
なぜ、ここまで人はあたたかくなれるのでしょうか。人の心の美しさを感じます。
寛容であることは美徳ではある。しかし、ダメなものはダメですよ。
プロダクトに関してはね。この場合、作品については。
この寛容さと作品に対する曖昧な態度はどこからくるのか。
ダンスに関する言説の多くは、作家と作品を混同している。もちろん、作家としての評価は作品の評価と不可分である。しかしながら、作家、つまり生きている個人、に対する思い入れと、関係性などが、作品に対する正しい評価を曇らせてしまっていると思う。
結果として、作家についての言説も育っていないのではないか、というのが僕の持つ疑念である。
このことは重要なので、またあらためて書くことにしたい。
自分達の組織を分析する [ dance ]
先のエントリでも触れたが世田谷パブリックシアターでおこなわれているセミナー「観客創造にむけて~自分たちの組織を分析する」に提出したワークシートを転載する。
質問の形式についてはP.F.ドラッカーの非営利組織の自己評価手法によるらしい。
# 一部の記述については提出時より加筆した
1. 「使命(目的)」
私たちの使命(目的)は何か?
マクロ的には
世界平和を実現するため。
世界から暴力を追放するため。
ミクロ的には
作家(振付家)の自己満足のため。
2. 「観客」~現在の観客と今後の観客
<現在>
誰が観に来ているか?
(正確に把握は出来ていないが)
観客の半数
a. 出演者の知人
残り
b. コンテンポラリーダンスのファン
c. リピーター
その人たちはどこにいるか?
東京周辺でしか公演をおこなっていない関係もあり、ほとんどが東京近郊在住である。
cについては、男性(30~40代)が中心である。
※コンテンポラリーダンスの客層としては異色かもしれない。ただし彼らはほとんど1人でしか来場しないようだ。
<今後>
誰に観に来てもらいたいか?
(普通に)通勤、通学をしている人。
暴力が日常的である世界にいる人。
その人たちはどこにいるか?
どこにもいないだろうし、どこにでもいるだろう。
これから探さなくてはいけない。
前述したとおり、観客の多くは出演者の知人であるのだが、「知っている」というメンタリティは無視することができないと思う。知っている、からこそ作品の意味を難しく考えることなく自然に受け入れる心理状態が観客の側に生まれるのだ。作品性を訴えることも重要であるが単純に作家、出演者を認知させる機会を増やすことも重要であると思う。
3. 「提供物」
私たちが提供しているものは何なのか?
①強み
観客が想像し考えることが出来る作品である。
②弱み
ダンスっぽくない。
分かりやすくない。
面白くない。
③他の団体との差別化のポイント
他のコンテンポラリーダンスの団体の作品と較べるなら、子供っぽくない、大人の作品であり、社会人たちの鑑賞に堪える。
とはいえ、コンテンポラリーダンス業界自体が狭い世界なので、他団体との差別化はあまり意味がないのではないかと思う。
(追記)
初回の自己紹介のときにも言ったことですが、私たちの課題は観客を増やすことより、質のよい観客を育てることにあると思っています。
残念ながら、あえて語弊のある言い方をするなら、今のコンテンポラリーダンスの客層の質は悪いと思います。質が悪い、ということはどういうことかというと、感受性が低い、自らの言葉で考えることの出来ない観客が多い、ということです。そして、困ったことに、その観客を受容しているのが、ダンス界であり、その言説をリードしている批評家たちであると思います。別の言い方をすれば、批評家たちの貧困な言説にダンスの見かたが規定されてしまっているのではないか、という疑念をいだいています。
ダンス、特に私たちがやっているような作品、はけっして分かりやすいものではありません。だから言葉に左右されることも多いのです。と同時に、言葉による先入観さえ持たなければ、分かりやすいものであるとも言えるのです。それは、私たちの知人である観客、普通の会社員たち、の意見を聞いても明らかなことです。
では、私たちは、どのようにダンスを広める、そのための言説を作り上げる、のか。
そのことを考えていきたいし、実践していく必要があります。
そのための具体的な施策についてはこれから明らかにしていきます。
話すこと、ダンスを取り巻く世界のこどもっぽさ [ dance ]
3/2にニブロール公演「no direction」を観にいった。作品について書きたいことはない。この日の公演終了後におこなわれたアフタートークに関連したことを書く。
アフタートークって何でやるんですかね。僕がアフタートークに残った動機付けもただその疑問に尽きる。
トークの出席者である小崎哲哉氏は「こどもっぽい」という形容を何回か使った。その用法は一般的な使われ方と同じく否定的な意味合いであったと思う。
いや、君が、小崎さんが、今そこでいる状況がこどもっぽいじゃないの。君たちは砂場で遊んでいるこどもたちにしか見えないよ。
その場で何を目的としてそこに立ち、座りでもいいが、何を話すのか。君たちは何も考えていない。
その自覚すらない。
ダンスを伝えるためには作品を上演するだけでは足りないと思う。伝わらないと思う。ダンスについて話す機会も必要だと思う。
だからこそ、話すことについては慎重にならなくてはいけない。考えなくてはいけない。
不用意な会話は特定の作品、公演のみならず、すべてのダンスにとって害となる。
話す機会、それがアフタートークであるとすれば、それが作品を補完するものなのか、観客へのファンサービスなのか、明確でなくてはいけない。
その問題意識はトークの主催者、出席者もすべて明確にしていなければならない。それが分かっていない、曖昧な人は参加するべきではない。
何より、アーティストが考えよ。人任せにするな。
つなぐ [ dance ]
週末は、手塚夏子の自宅カフェ&バーにおじゃました。
彼女は自身のアーティストとしての活動のみならず、アーティストを結び付ける活動をやっていてカフェ&バーもその活動の一環といえる。
今の日本のコンテンポラリーダンスのシーンでは、アーティスト達はそれぞれの孤独な作業に追われていて、ダンスを語る言葉は創作の現場の外から、批評家、制作者、観客などからしか発せられない。そのため、アーティストは自分自身の作品の意味、社会性についてすら、考えること、発信することを放棄してしまっているのではないだろうか。アーティストにはもっと考えること、発信すること、つまり言葉にするということ、が必要だ。
そのためには、アーティスト同士がそれぞれが抱えている問題について気軽に話し合う機会も必要だろう。それは多くのアーティストも思っていることのようだ。と同時に、具体的な、目に見える動きを、そのような場から作っていかなくてはいけない。少しずつ、一歩一歩。直近の目標を決めよう。
変化 [ dance ]
僕は変わった。それは昨年(2006年)の10月頃からだろうか。
ここに書いていることもずいぶん変わってきたと思う。以前は、こんなエントリも書いていた。今は、他のアーティストの公演も出来るだけ観に行くように心掛けているし、積極的に彼らと関わりを持ちたいと考えている。
僕は自信がなかった。一度活動を止めてしまったこともあり、仕事をしながら活動することが可能かということ、意味のある作品が作れるかということ、何より活動を続けるモチベーションを維持できるかということについて。
「明晰さは目の前の一点に過ぎない。」を制作、上演することが出来たことで、ようやくアーティストとしての自信を持つことが出来るようになった。
そして、その直後に参加したイタリアツアー「カタチを超えて」での体験、海外の見知らぬ人々に作品を見てもらったこと、同行したアーティスト達とダンスに関する問題意識を共有できたこと、その影響がある。
そのとき、自分達はこのままで良いのだろうか、という疑問が湧いてきた。もう文字通りに踊らされている場合ではない。自分達がダンスを取り巻く環境を変えていく、ムーブメントを作る、そうしていかなくてはいけない。
そのためには、何度も繰り返しているように、メディアが必要ならメディアを作る、劇場が必要なら劇場を作ればよい。
まず一番最初にやることは、アーティスト自らがダンスについて語る言葉を持つことが必要だ。
アーティストの皆さん、会話しましょう。
山脈 [ dance ]
少し日が開いてしまったが、2007/2/3に、こまばアゴラ劇場で上演された神村恵カンパニー「山脈」の感想を書く。
神村恵は、大橋可也&ダンサーズの作品に出ているからという理由からではなく、そのダンスに対する懐疑の姿勢、動きへのこだわりから、今の日本のダンスの可能性を考える上で欠かせない作家の1人である。
はじめてのカンパニー作品「山脈」には僕も刺激を受けたいという気持ちを持って観に行った。
まずは印象に残ったところから。
やはり神村の走る姿は良い。ダイナミックだが無理がない。そこに気づいていた僕は自分の作品にも既にその姿を使っていたのだが。
作品中盤に神村と4人のダンサーが向かい合ったシーンは、より大きな関係性への発展を期待させた。しかし、その後、他のダンサーも同じような配置となったのはその印象を打ち消すもので、残念に感じたのだった。
次に、思ったこと、疑問に感じたことを書いてみる。作品と直接結びつかないこともあるが、考えることが出来るのは、それだけ良い作品であったということなのだろう。
幾何学的
アフタートークで批評家の武藤大祐氏が言っていたことであるが、「幾何学的」なシーンがある。神村はそれを「好きだから」という理由で採用したと言っていた。
幾何学的、というのは比喩に過ぎないのだろう。幾何学に基づいて振付を考えているわけではない、おそらく、と思う。
では、幾何学的とは。その比喩が持つ意味とは。
僕には分からない。
分かるのは幾何学的であってもなくても、ある造形、空間配置が連想させる関係性である。その関係性にこそ興味がある。幾何学的という比喩は必要だろうか。
群舞
なぜ、ダンスでは皆で同じ動きをするのだろう?それがダンスだといえばそうなのだろうし、それが振りであるといえばそうなのだろうが。
教育的な意味はあると思う、皆で同じ動きをすることの。
しかし、ダンス作品の中に現れる同じ動きの意味とは。
これもよく分からない。
僕も同じ動きをするという振りを取り入れたことはあるが、あくまでダンス的なことのパロディーであった。今はそんなことをする必要はないからやらない。
では、どうして作家はチョイスしたのか、これは聞いてみたい。
表情
開演当初、舞台上のダンサーたちの表情は硬かった。初日だったこと、客入れに時間を要し開演が押したことが影響したのだろうが、その表情が空間全体を凍りつけてしまっていた。いろいろ動きがあったにしても空間は動かないままだった。
作品中盤でダンサーたちが走り出してから、当然ながら心拍数が上がることもあり、表情は緩んできて、それとともに空間もダイナミックに変貌してきた。
表情に重きを置いていない作品、おそらくは、にも関わらず、こうも表情の変化が作品に影響するとは、僕にも新たな発見であった。当たり前のことかも知れないが、表情も振付の、作品の一部なのだ。
これも作家の意図を聞いてみたい。
平等
ほとんどのシーンでダンサーたちは平等な存在だったと思う。しかし、そのことがダンサー個々の存在を薄くしてしまったように感じられた。
世の中にほんとうに平等な関係性などあるのだろうか。平等でないからこそ、流れが生まれる。
沈黙
動きへのこだわりに反して、照明や音響についてはその必然性を感じなかった。そこまでコントロール出来なかった、あるいは意図してしなかった、ということであろうが。
語りえないことについては、沈黙するほかない。
沈黙こそ僕たちに必要なことなのではないだろうか。
テクニック [ dance ]
これも「超詳解!20世紀ダンス入門」での議論から。テクニックが持つ意味とは。
大貫秀明氏、馬場ひかり氏がテクニックに関する質問への答えとして話したことは次のようなことだった。
テクニックとスタイルを混同してはいけない。作品に直接用いられることがなくてもテクニックを磨くことはダンサーにとって必要である。
もっともな意見のように思える。
しかし、もしそうなら、ダンサーに必要なのはダンスのテクニックではなく、身体訓練なのではないか。
そこには重要な視点が抜けている、あるいは自明のこととして看過されているように感じられるので、補足をしておきたい。
ダンスは舞台作品としての面もあるが、現在の社会においては教育としての役割、需要がはるかに大きい。そのため、多くのダンサーたち、批評家、研究者も教えることで生活をしている。
さらに教育を経済活動して捉えたとき、テクニックは商品と考えられる。
新たなダンスの一派が、新たなテクニックを開発しようとするのも、商品を差別化し顧客を拡大するためである。ここに良い、悪いという価値観は当てはまらない。ごく自然な経済活動、というより自然な行動だから。
翻ってみるに、教えをしないダンサー、振付家、大橋可也とか、にはテクニックは必要ないのか。
少なくとも名前付きのテクニックはいらない。売らないのだから。
無名テクニック?語感はいいが、それをあえてテクニックと呼ぶ必要もないだろう。
というわけで、僕たちはテクニックとは無縁であると断言しよう。
暗黒舞踏 [ dance ]
暗黒舞踏の振付法の特徴について、以下に私見を述べる。
1. 身体概念の拡張
遠くの小枝、内臓の中のこびと。
身体から遠く離れた地点から出発する、あるいは身体の中に入っていく。
ラバン等が個人の身体を軸にした動きから舞踊を考えていたことと比較すれば、発想の出発点が違うことがあきらかだろう。
2. 主客の倒置
絵を見ていた人物がその絵の中の人物になってしまう。
主体と客体が入れ替わる。そのときの軸となるのは視覚、聴覚などの感覚である。
1と2によって、人間性を解体し再構築するプロセス、それが暗黒舞踏の振付法なのだと思う。
人間性への懐疑、それはポストモダンと呼ばれる芸術活動に共通するテーマだろう。そう考えれば暗黒舞踏とジャドソンダンスシアターなどのアメリカのポストモダンダンスと重なる面も大きい。ただし、アメリカポストモダンダンスがダンスの枠組みにこだわるところから始めたことに対し、暗黒舞踏は人間存在そのものに直接目を向けた。
暗黒舞踏の振付法の可能性はまだまだ残されている。
そして、振付法の実践に土方巽の語彙にとらわれる必要はない。
舞踏の、暗黒舞踏に限らず、技法と作品作りは違う、という。「超詳解!20世紀ダンス入門」での國吉和子氏、正朔氏もそのようなことをいっていた。土方巽自身にも技法と作品の乖離はあっただろう。技法の進化とは対照的に、作品作りの枠組みは解体されていなかったと思う。
技法の追求によって作品をより意味あるものに推し進めることはできないのか。
それは僕たちがやろうとしていることである。
僕たちの活動は暗黒舞踏の影響下にあるのはもちろんだが、暗黒舞踏を継承し発展させる試みでもあるのだ。
カルト、フレームワーク [ dance ]
先週末も「超詳解!20世紀ダンス入門」に参加した。
第5回目は土方巽と暗黒舞踏についての回であった。実のところ、その回で上映された映像は既に見ているものであったし、正朔氏による実演も、ほとんど知っている語彙に基づくもので、目新しいものはなかったといえる。
# 土方の語彙が流通していること自体は興味深い
しかし、舞踏について考える機会になったと思う。以下、思ったことについて書くことにする。
会のときにも質問したことであるが、僕にとって意外と思えるのは、秘密主義といわれていた70年代の技法完成期から80年代に入り、土方自身が一般向けのワークショップを開催し、その技法を明らかにしたことである。
その変節と思える行動にはどのような意味があったのだろう。
國吉和子氏の答えは、「よく分からない」であった。
おそらく、土方自身の変化については分からないだろう。しかし、興味があるのは土方個人の問題ではなく、舞踏と社会の関係の変化である。
70年代に土方のところへ集まってきた若者達は何も求めてきたのだろうか。
舞踏を学びたいから?いや、社会からの逸脱を望んでいたのだと思う。秘密主義を目指したというより、結果として秘密主義になっていたのであり、ある種のカルトであったといっていいと思う。
暗黒舞踏では、身体をからっぽにするとか、飛び込む、という言い回しが用いられるが、その頃に暗黒舞踏を始めた若者達は、既にからっぽであり、飛び込んでいた。
舞踏と社会の関係自体が、舞踏の技法のフレームワークであったといえる。
では、80年代にその関係はどうなったのか。
これも憶測でしかないが、既に社会からの逸脱というテーマが若者達から無くなってきたと思う。それと反対に、カルトの一般化と商業化、すなわち新興宗教の隆盛や自己啓発セミナーの流行が生まれてきた。
そうなれば、もはやフレームワークは機能しない。
このことは今の僕たちにも共通する問題である。
僕たちのダンスはカルトになることも出来ない。別のあり方が必要だ。
社会との関係性をフレームワークとして捉え直し再構築していくこと。
意識の誕生 [ dance ]
舞踏は"do"ではなく、"be"であるという。
モノになるときに、なろうとイメージするのではなく、既にそのモノなのだ。
では、その時の僕たちの意識はどこにあるのだろう。
上手い説明は聞いたことがないし、説明できない。
人類は3000年前まで「意識」を持っていなかった。意識を持つまでの文化は、神の声を右脳から聞き、それを左脳が実行する「二分心」によって成立していた、という説がある。
その真偽はともかくも意識のあり方の説明としては興味深い。
非暴力 [ dance ]
ダンスを舞台作品として上演する目的は、作家によって、作品によっても異なるのは間違いない。
しかしながら、ダンスが非暴力を訴えていることに異論を挟むものもいないだろう。
ダンスを見るものが自らの身体に気づくこと。それが僕たちが望んでいることだ。
ダンスを見るためにダンスをする必要はない。ダンサーのような身体である必要もない。
しかし、自らの身体に意識的であってほしい。
身体に意識的であるとはどういうことか。
まずは健康であろうと努力することだ。もちろん、誰もが健康でいられるわけではないし、健康といってもあらゆる形がありうる。その人なりのやり方でよい。
健康であろうと努力することが出来るにも関わらず、それを怠ることは、自らの身体を傷つけているに等しい。それは暴力である。その人のみならず、その人の近親者に対しても暴力を振るっているのだ。緩慢な自殺といってもいい。
そういうわけなのでぼくはこれからも決してWSを受けたりしないでフツーに、ただし体にはフェチに、生きていようと思う。
ここには誤解がある。
しかし、僕たちが重要なメッセージを伝えられていないのも事実なのだ。
アルゴリズム [ dance ]
批評家とか研究者は、観客も、何でも分類したがるものだ。
けっして、それが悪いというわけではない。自分の頭の整理には分類は必要。
しかしながら、カテゴリー、ジャンル分け、ということが既に時代遅れになってしまっている。
現実界はとっくの昔にスーパーフラットですよ。GmailのUIを見ればよい。
すべてはフラットに配置されているとすると、それらを検索し、関連付け、レーティングするためのアルゴリズムがある。ダンスを見て、感じる、考えるためのアルゴリズム。
優れたアルゴリズムの開発者こそ、優れたオーディエンスと呼ばれるべきだろう。
ダンスマップ [ dance ]
日曜日(2007/2/4)に「超詳解20世紀ダンス入門」の第一回に出席し、木村覚氏のレクチャーを聴いてきた。
とくに目新しい価値観、概念の発見はなかったと思うが、現代のダンスを俯瞰する試みは意欲的だと思うし、紹介された作品の映像も参考になるものが多かったので、出席できたこと自体よかったと思う。
# 段取りが悪いところはダンスを取り巻く環境の構造的な問題に起因するものだと思うが、ここでは触れない
木村氏がレクチャーで使用した図を氏のブログから引用しておく。
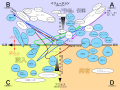
この図は力作だと思うし、これだけ見ていてもそれなりに興味深い、面白い。
しかし、僕たちはダンスを作る側、あるいは見る側としてレクチャーに参加しているわけで、この図だけを理解することが、僕たちの活動、作る/見ることに役に立つのだろうか。僕たちには作る/見るためのガイドライン、のようなもの、が必要だと思う。そのベースとなるのがこの図なのだろうか。
いや、きっとそうではないね。
この図は僕たち自身が書くものだ。自分なりのダンスマップ、適当に命名しておく、を書いていく過程が、作る/見ることの意味づけを再定義することになると思う。
とはいえ、木村氏作の図のようなものを作ろうとするとたいへんだ。途中で断念してしまうね。それに、いくら頑張って作ったところで、それが個人の頭の中にしかなければダンス全体を考えたときには意味がないんじゃない。
ここでアイデア。
ダンスを構成するアクターに対して自由にタグ付けと重み付けが出来るインタフェースがあり、そこに蓄積されたデータに対してビューポイントを指定すると、マッシュアップされた結果がマップになる、っていうのがいいじゃない。
例えば、木村氏のタグ/重み付けでいくと、大橋可也&ダンサーズは「タスク性, 5」とか。
# ここでいうアクターは木村氏の図だと振付家/カンパニーだが、必ずしもそうでなくてもよいと思う
# マップのビューポイントは自由に変えられる
# タグ自体にタグ付けしてもいい
ダンス2.0っぽい。
では、これを実現する仕組み、フレームワークは誰が作るのか。
先のエントリの繰り返しだが、表現者なら自分で有効なメディアを作るべきだろう。
僕がやりましょうか。
ダンスとメディア [ dance ]
前回のエントリに書いたことの続きであるが、ダンスを取り巻くコミュニケーションツールの未成熟さについて、堤広志氏がwonderlandに寄稿したらくだ工務店「幸せのタネ」(上)で、メディアの問題を取り上げていたので引用する。
専門外であるメディアがあたかも「ガス抜き」をするかのように、エキセントリックでキワモノ的な事例を中心に大々的に取り上げる傾向が目立った。実際、各メディアの編集者の不勉強により、企画を一部の批評家や研究者などに丸投げしてしまうような杜撰な仕事も見受けられ、記事内容にも偏りが出たり、バイアスのかかった見方や紹介の仕方をするものも少なくなかった。
メディア、ここではマスメディアのことを指していると思う。上記のような傾向については、既にダンスに取り組んでいる人々は認識していたと思うが、メディアに関わる人から意見が公にされたことは重要である。
ダンスにマスメディアが与える影響は大きい。そして、現場に立ち会うことの出来る人間は限られていて、その少数の目撃者の見解のほかに流通するものがない、ということはダンス上演の根本的な構造に関わる問題である。
では、どうすればいい?
研究者なら自分で速いコンピュータを作るべきである。アラン・ケイ 東大での公演より
表現者なら自分で有効なメディアを作るべきか。
コミュニケーション、ダンス、テクノロジー [ dance ]
ダンスとは関係性だとか、コミュニケーションだとか、いつも言っていることだ。
だが、ダンスを伝える形式、作品上演、批評、情宣、などなど、はコミュニケーションツールとしての機能を果たしているだろうか。
コミュニケーションとコラボレーションと題する興味深い記事があったので、コミュニケーションスタイルの分類の項を引用する。
【タイプ1 = 送る側:能動的-受ける側:受動的】 … 電話、メール、インスタントメッセージ【タイプ2 = 送る側:能動的-受ける側:能動的】
… BBS、Blog、ファイル共有【タイプ3 = 送る側:受動的-受ける側:能動的】
… フォークソノミー【タイプ4 = 送る側:受動的-受ける側:受動的】
… リコメンデーションシステム
僕の作品は、ここでいう能動的/受動的の関係性自体を問いかけることから出発している。
しかし、その上演となると、演者:能動的、観客:受動的、という固定化された関係性に帰着してしまっているように思う。
この問題については引き続き考えていかなくてはならない。
フォークソノミーのようにインターネットをベースとしたテクノロジーの進化によって、新たに生まれたコミュニケーションの形式もある。ダンスの現実はその進化とは無縁なのではないか。
こと、ダンスとテクノロジーというと、マルチメディアを用いた作品とか、モーションキャプチャーなどの技術をダンス作品に取り入れるとか、逆にダンスをそれらに提供するとかのアプローチを思い浮かべてしまう。しかし、そんなのはダンスの本質と関係ないだろう。
テクノロジーがいかにダンスの本質を、コミュニケーションの可能性を、そのエッジを先鋭化させるか。これも大きな課題である。
境界線 [ dance ]
先日のエントリでも書いた1/21に神楽坂die pratzeでおこなわれた「ダンスがみたい!新人シリーズ(Kグループ)」についての感想を書く。
3組の上演を見て思うことは、ダンスを見ること、見せることは、誰のため、何のためなのだろうか、という疑問である。その疑問については、ずっと考えていかなくてはいけないだろう。個々の上演についても思うことはあるのだが、ここでは、関かおり・木村美那子の作品「だんだら」を見て思ったことのみ書くことにする。
言ってみれば身内なわけで、どうしたって見かたは甘くなってしまう。
演出的にはよく出来ていると思う。興味深いムーブもいくつかあった。しかし、何か物足りない。
適切な表現がどうか分からないが、文学的な作品なのだと思った。文学的である、ということは、舞台上の世界を解釈出来てしまう、ということにつながる。解釈出来るということは、見る側にとって舞台上の世界は自分の外の世界に留まってしまうのではないだろうか。いくら奇妙なこと、おかしなことが舞台上でおこなわれていていたとしても、それは自分の世界の出来事ではない。
ダンスは僕たちの世界の境界線を描き直すものだと思う。想像したことのない境界線を描くダンス、それが見たいし、やりたい。
小劇場 [ dance ]
先週土曜日(1/20)に神楽坂die pratzeでおこなわれた「ダンスがみたい!新人シリーズ」を観にいった。理由はダンサーズのダンサーでもある関かおりが木村美那子とのデュオで出演するからである。内容についての感想はまたあらためて書くことにする。
観にいった経験から感じたことを書く。
僕たちが劇場に着いたのは開演10分前ぐらいであった。既に客席はほぼ満員であったが、何とか席を確保することが出来た。それまではよい。
それ以降も観客は続々訪れ、桟敷席も2列になってしまい、開演したのは20分押しであった。その日は3組の上演があり、途中10分の休憩が予定されていたが、満席であることの影響で、その休憩も20分になってしまた。
よくある小劇場でのひとコマといえばそうだし、僕たちも慣れているといえば慣れているのだが、今の自分たちの時間間隔や体調を考えると、料金は倍でいいから、ちゃんとした椅子席に座らせて欲しい、時間通りに始まって時間通りに終わって欲しい、という気持ちが頭をもたげてくる。小劇場に足を運んだ経験のない人が、40、いや50、60過ぎてから、小劇場に行こうという気になるのだろうか。敷居が高いように思う。作品の内容は措くとしても。
小劇場が、やる側も見る側も若者たちのものであるのなら、今のままで良いだろう。しかし、これから、既に今もそうなのだが、高齢化社会において小劇場のあり方も変わっていくべきだろう。
その変化に僕たちはどう関わることが出来るのか。
「CLOSURES」作品メモ [ closures , dance ]
「CLOSURES」当日パンフレットに載せたメモです。[[Sample Code of Closure (JavaScript)] function closureSample() { var count = 1; return function (arg) { count += arg; return count; } } function useClosure() { var closure = closureSample(); for (var i = 0; i < 5; i++) { alert(closure(i)); } } result: 1 2 4 7 11
「もう一匹のネコはどうした?」と、彼はたずねた。
(中略)
「お前は自分がマックスのようだと思っており、そのためにもう一匹のことは忘れてしまった。その名前さえ知らない。」
~カルロス・カスタネダ「未知の次元」より~
比喩 [ dance ]
僕たちはどうしたって人にものを伝えるためには、何らかに喩える、ということが必要だ。
しかし、これが大問題。
喩えで理解しないこと。そのものを理解すること。それがダンスに出来ることであり可能性だと思う。
なのに、最近の僕の文章も、たまに比喩表現が出てきて気持ち悪い。
比喩に依らないこと。
ナルシシズム [ dance ]
「CLOSURES」の感想でも、「ナルシシズム」という語彙が何件か見受けられた。作品の解釈は自由だし、それに異議を訴える必要もないのだが、言葉の使われ方に疑問を持ったので少し言及しておく。
おそらく多くの人はナルシシズムという単語をネガティブな意味合いで使っている。上記の感想を述べた人にしても、作品についてネガティブな意味として使っていたと思う。
ナルシシズムはけっして悪いものではない。しかし、時には機能障害として現れる場合もあり、コミュニケーション不全を引き起こす原因ともなる。
「CLOSURES」で着目しているのは、このコミュニケーション不全の問題である。
今の僕たちを取り巻く虚構の美、悦楽、表層だけのコミュニケーション。それらは個々人に植え付けられたナルシシズムに立脚しているのではないか。そのナルシシズムの果かなさ、無意味さを作品では取り上げていたのだけれど。
うまく伝わっていないとすれば、未熟だということか。
身体の空虚さ [ dance ]
1/17(水)にクラシックスでおこなわれた灰野敬二(音楽)/居上紗笈(ダンス)のイベントを観に行った。目的は近々クラシックスでおこなわれるイベントに自分たちが出るからで、その下見である。
まず、下見の感想。
クラシックスはかつてのジャンジャンの跡地にあるという事前の認識だったので、ある程度の広さはあるのだろうかと思っていたが、狭い。旧ジャンジャンの楽屋、倉庫スペースなのだろうか。狭い教室みたいなもので、とうてい踊りを見るには適さない。
僕たちがやることはこれから考える、そうこれからなのだが、コンセプトが明確なもの、大橋可也&ダンサーズだと一目で分かるものにしないといけないと思う。音楽のイベントだが、おそらく音は使わない。音があると身体を見なくなってしまう。
あとは、イベントを見ての気づき。
今さらながら灰野敬二氏のパフォーマンスは初めて見たのだった。予想していたとおり、面白かった。色々なものたちを使っての音出し、音自体もさることながら、その身体の明晰さ。一見、挙動不審な、でたらめな動きは、ぶれがない、迷いがない。
それもそのはずである。ミュージシャンは音だけをイメージしていて身体をイメージしているわけではない。言葉を替えると身体動作の目的性が明確なのだ。
翻ってみるに、ダンサーの身体のなんと空虚なことか。ダンスにおける身体動作は基本的に無目的である。徒手空拳というが、その身体は寄るところなく移ろいやすい。
ダンサーの身体とそれ以外の目的を持った身体、これらを並列に配置することは、ダンスに取り組む僕たちにとって大きな危険性をはらんでいる。空虚な身体はいつでもかき消されてしまうだろう。
しかしながら、ダンスの本質とは、まさしくその空虚さに他ならない。空虚さによってこそ、ダンスをおこなうもの、見るものに、無限のイメージの扉を開くのだ。
空虚さを扱うことに注意をはらうこと。
不安 [ dance ]
ダメ出しをしないことにも関係するのだが、ダンサーだけでなく、スタッフも作品の最終形がどうあるのかが、分からず不安を感じさせてしまっていると思う。
僕自身はこうあるだろうな、こうあればいいな、と思うことはあるのだけど、その価値判断も日々変わるものであるし、毎回その思いを語っていては、かえって不安にさせてしまうだろうと思って、出来るだけ今やるべきことと抽象的なビジョンだけを語るようにしている。それが正しいやり方なのかどうかは、正直よく分からない。最終的なアウトプットについては、少なくとも僕自身は満足いくものになっているので、結果として正しいやり方だったと言えるかも知れない。
ダンサーに振りをつける時点でも大きく直さない。僕が持っていたイメージと違ったとしても。違うことをどう捉えて作品に活かすかは僕の仕事だと思っているから。稽古を重ねていく過程でも、出来るだけ振り自体は変えないで進めていく。全体がある程度組み上がった段階で、うまく活かせていない部分については、大きく振りと構成を直すことにしている。このあたりの修正のタイミング、動機付けもダンサーたちはあまり伝わっていないと思う。僕の中では整合性は保たれていてほとんどの変更は想定内のことではあるのだが。
彼らとのコミュニケーション方法については改善しなければならないと思う。そのためには作品とその作り方に対するお互いの理解を深めていく必要がある。その方法として、会話することももちろんだが、枠組み、体制を用意することも考えなくてはならない。
きっかけ [ dance ]
舞台作品には「きっかけ」というものは付き物だ。なのに、僕の作品では、ほとんどきっかけがない。
きっかけがはっきりあるのは、音出しぐらい。曲で尺を決めている場合があるので、音出しのタイミングが狂うと尺が狂ってしまうこともあるからだが、それも作品による。照明は基本的になんとなくだ。
1つの理由としては、僕が嫌いだからである。間違えることを考えると緊張するじゃないですか。同様の理由で「板付き」も嫌いで、やらない。
もっともらしい別の理由は、きっかけを持つことで各々の要素、ダンサー同士、音楽、照明など、が相互依存の関係を持ってしまうことを避けたい、ということがある。依存の度合いが増すにつれ、そのための稽古やテクリハが必要になり、本来の振りの稽古に時間が割けない。作品構成上から見ても、舞台上における各々の存在を狭い世界に閉じ込めたくないのだ。
もちろん、きっかけがないことによって、考慮しなければならないこと、稽古しなければならないことも増えるのだけど。
ダメ出し [ dance ]
僕はダメ出ししません。今や一般人でもダメ出しするのに。テクニカル面においてはダメを出すこともあるが、それも、こうしたほうがいい、というレベルで、こうしなければならない、というケースは稀である。出演者にはほとんどダメを出すことはない。
何故か。僕にとっては、ダンサーがある振りを出来ていない、ということはないのだ。もちろん、こうあって欲しいと思うことはあり、そのための指示、サジェスチョンはするけれども。もし、出来ていない、ということがあったとしても、作品が成立するように作っているつもりだから。
出来る限りルーズに作る、どう転んでも成立するように作る、これは僕が作品を作る上でのモットー。
ダンサーは不満に思うことがあるかも知れない。ダメ出しされないから、かえって自分のやっていることが正しいのか、自信を持てないこともあると思う。
この問題については、また改めて書く。
やっぱり演劇は嫌い [ dance ]
演劇、と呼ばれる舞台作品、を観ての感想を書く。
昨年(2006年)末にBankArtStudio NYKでおこなわれた、ARICAの「キオスク」公演を観た。ARICAについては、いくつか良い評判を聞いていたのと、いわゆる演劇らしくなさそうなイメージなので、演劇嫌いの僕でも大丈夫そうかなと思ってとのこと。
しかし、やっぱりダメだった。
セリフはごくわずか。多分、その量は大橋可也&ダンサーズと同じくらい?で、舞台上でおこなわれていることの多くは身体所作である。そして、この量も大橋可也&ダンサーズと同じくらい?なのだが、この所作に僕は拒絶反応を起こしてしまう。
ペットボトルに水を入れたりしているのだが、ペットボトルを持つときにわざわざ大きく腕を回し意味ありげに掴む。なぜなのだろう?演出家の意図は分からない。だが、僕が思うには、行為を行為として見せるためには行為が成立する最低限の身体の動きに留めなくてはならない。でなければ、行為自体の意図、目的性ではなく、行為をおこなっている演者の意図が前面に出てきてしまう。
ペットボトルとの絡み、新聞を折り続ける行為、それらは面白いとは思った。だが、演者から声が発せられるとき、そのセリフは舞台上の情景の説明に過ぎなかった。僕は舞台上の行為の関連をぼんやりとしてしか把握していなかったのだが、説明を聞くと、キオスクとその周りにいる人たちの関係を演じているようだ。もっとも説明を聞くまでもなく、理解出来てしまうような関係なので、それまではっきりと気づいていなかった僕が変なのかも知れないが。舞台上の出来事を説明してもらったとして、それが理解出来たとして、何が嬉しいのだろう。そんなことを求めて舞台を観に来ているのだろうか、僕たちは。
大きな疑問が残った。
犬 [ dance ]
たまには他人の作品を観た感想を書いてみる。作品を評したいわけではないので、あくまで僕の視点からの感想として。
昨年(2006年)末にアゴラ劇場で、金魚の「犬の静脈に嫉妬せず」を観た。観る動機付けとしては、僕たちもアゴラでの「CLOSURES」公演を控えていたので、その参考にしたい、というのが第一ではあったのだが。その理由のため、ダンサー全員にも観劇させた。ついでにいえば、舞台面がコンクリ打ちっ放し(常設のパンチカーペットをはがした状態)だったので、同じ舞台面にしようと考えていたこともあり、良い参考になった。
もう1つの動機付けとしては、純粋に若い作家の作品に興味がある、ということ。
第一印象としては、好感が持てる、ということだろうか。振付家の鈴木ユキオ氏が自身のブログや当日プログラムに書いていたように、踊りへの懐疑に正面から立ち向かっている印象を受けた。
以下は、気づいたことなど。
ダンサーの動きとしては、身体を叩く、倒れる、首を振る、などの動きが主だ。大橋可也&ダンサーズにもよく出てくるような動きといってよい。多分、ダンスじゃない動きをやろうとすると、こうなってしまうんだろう。そこは納得。しかし、いくら激しく叩いても倒れても、リアルな痛みが伝わるわけじゃない。振付、決められた動き、なんだから限界がある。「CLOSURES」では皆木は肋骨を折っていた。倒れる稽古をしての結果なのだが、だからといって痛みが伝わったか、というと疑問であり、肋骨を折っているという情報を伝えたとしても、あー大変ね、あるいは、バカじゃないの、ぐらいの印象しか持たれないと思う。僕自身の印象にしてからそうだ。より明確な方法論が必要だろう。それは僕にとっても同じ課題である。
コンタクト。ダンサー同士の接触がある。これは僕はやらない。全部やらないわけではないので、やるケースについては後ほど書く。コンタクトも諸刃の刃だ。激しくやればやるほど、プロレス(特にルチャリブレ)などに近づいていってしまう。プロレスが悪いとは思わない。僕はプロレスは大好きだし、レスラーには敬意を抱いている、とともに、彼ら痛みの専門職には敵わない、のだと思う。僕たちには別の方法論が必要だ。
更に、男女のコンタクトがある。女が男を抱えて投げる。作家の意図は分からないが、これは意味がないと思う。単なるダンスの振付にしか見えない。逆なら意味がある。男が女を抱えて投げる、コンクリの床に叩きつける、のなら。そうすれば暴力となる。
で、僕がやるコンタクトのケースは、「CLOSURES」で用いたように、特権的な力を持った人物が他の人物を操作する、というものだ。コンタクトにおいては接触以前にダンサーそれぞれの関係性を明らかにしておく必要がある。接触によって関係性が変わる、変わらないにせよ、そうしないと単なる動きとなってしまう。動きそのものを主題としているのならそれでよいだろうが。
場面転換。これはまったく理解できない。僕も和栗由紀夫+好善社の公演に出ていたので、舞踏の作品構成については理解しているつもりだし、シーンを分け、その場面における演者の役割を決めてつくる、というやり方は分からないわけではない。舞踏特有なのではなくダンスにおいて一般的な作り方かもしれないが。しかしながら、今回の金魚の作品では場面転換は意味を成してなかったと思う。
舞台上にいるダンサーは誰なのか、何なのか。場面転換によってその存在は切断され、見えなくなってしまう。その存在が見たいのに。
僕は場面転換はやらない。シーンを分けて作ることもあるが、その時もダンサーの存在は同じであり続けている。その存在とその変化こそがダンスだと思うのだ。
家族の支え [ dance ]
多くのアーティストがそうであるように、大橋可也の活動も家族の支えによって成り立っている。特に妻の影になり日向になりのサポートは作品にとっても欠かせないものになっている。作品の内容面にフランクに意見できるのは彼女ぐらいしかいないのだから。
かつては、妻も自身のダンス活動をおこなっていたが、今は一緒にダンスに関わっていると思う。
よくある振付家、ダンサーのパターンでは生活面のパートナーが制作面を取り仕切っているが、僕たちはそうしていはいない。奥さんに制作をやってもらえばいいじゃない、と言われたことはあるが。制作、プロデューサーはアーティストとは別の視点が必要であり、利害関係も異なる場合も多い。家庭内に2つの立場の人間がいることは活動を長く続けるためには難しいと思う。
また、パートナーに経済的負担を強いることはしていないし、したくない。もちろん、男女間(男女でなくても)の関係性は人それぞれであって、何がいいとか悪いとかは一概には言えないので、他のアーティストの関係性を非難するつもりはないが。僕は、家族を養う分も含め経済的に自立して生きたい。妻の収入は自分のために使えばよいと思う。
作品を作る段階では、僕自身の精神的に不安定なこともあり、そのために妻に迷惑を掛けることもある。それについては申し訳なく思う。
犠牲としてではなく、一緒にものを作っている、という気持ちを持ってもらえるようにしたい。そのために僕も努力したい。
アーティストが作るもの、それは今の社会の価値観を一歩進めるものでなくてはいけないと思う。と同時に、アーティストの生きる姿勢、家族との関係も含めて、それも社会の進歩に逆行するものであってはいけないだろう。
差別化 [ dance ]
別に他のダンスカンパニーと差別化を図る必要もないと思うが、僕たちの存在価値を分かりやすく訴えるには他との比較も必要。
1つ、明らかなアドバンテージとして、出演者のバラエティが富んでいることが挙げられる。「CLOSURES」の出演者は20歳~42歳、多くのダンスや小演劇がそうであるように、特定の、多くは20代から30代前半に偏っていない。ロマンス小林の存在に拠るところも大きいってことだが。
出演者が特定のレイヤーに属していることはそれだけ舞台上の世界も狭まってしまうということだ。
影響 [ dance ]
「CLOSURES」は大橋可也&ダンサーズ史上もっとも地味、かつ笑える作品でした。
その地味ぶりには影響を受けたものがあるので、ここに記しておきます。
1つは、2004年のThe Kitchen公演でのダブルビルで一緒に上演したBeth Gill。
# 彼女の作品はドレスリハーサルしか見てないし、それも半分は寝てたのだけど
もう1つは、昨年末に森下スタジオで見た神村恵カンパニー。
僕は彼女達の作品が特に先駆的だとかは思わない。ただこんなに地味でもいいのね、分からせてくれたのは確か。
とはいえ、振付の方法がこれまでと大きく変わったわけではない。むしろ、より個人の内面に向かうようになっている。個々の内面から溢れるものが空間、時間全体を構成していく、このアプローチは僕のオリジナルだと思うし、こだわるポイントだろう。
観客創造 [ dance ]
月曜日(1/16)から世田谷パブリックシアターが主催するセミナー「観客創造に向けて~自分たちの組織を分析する」に参加している。
参加者は演劇の制作者が多く、ダンス関係、それも主宰/振付家は僕だけであった。
第一回のスピーカーである奥山氏と参加者の方々が、アーティストは観客を創造していくことに関心がないことが多い、というような発言をされていたが、それはおかしな話だと思う。
舞台作品をつくる、ということは、観客を創造する、こととイコールではないのか。
もし観客創造に関心がないアーティストがいるとすれば、失礼ながらその人をアーティストと呼ぶべきではないだろう。このセミナーにおいては、その性質上、制作者向け、マーケティング、という観点から議題が進められることが多いと思うが、作品を作る過程、姿勢、作品そのものが観客を創造していく道具立てにならなくてはならないと思う。
また、セミナーの自己紹介でも発言したことであるが、僕が関心があるのは、観客を増やすことではなく、良質な観客を見つけ出す、育てることである。良質な観客というと語弊があるかも知れないが、要は僕たちの作品を本当に必要としている人々のことである。
その人たちはどこにいるのか。もちろん、既に巡り合っている人もいるだろうが、今のダンスの観客層とは重ならないと思うのだ。
想像力 [ dance ]
僕たちの作品は観客の想像力を喚起させ、舞台上で起きていることを観客自身が意味づけることが出来るように作っている。
しかし、世の中には想像力のない人もいるというか、起きていることを描写することだけでしか作品との関わりを見出せない人もいる。どうして、そのような人が舞台を観に来ているのか不思議ではあるのだけど。得てして多くの舞台を見ている人がそうだったりするから問題だ。君たちに舞台ていうか芸術は必要ないと思うよ。
舞台、ダンスを普段観に来る機会のない人のほうが、想像力を働かせてくれていると思う。そりゃそうだ。自分が今ここにいることの意味を探すのは、人間として当たり前の反応だもの。
そう、当たり前のことなのだが、訴えていくことは必要だろう。想像力の重要さを。
笑い [ dance ]
コンテンポラリーダンスに分類されるダンスの公演を観に行ったとき、いやな気分になるのは、観客がクスクス笑うこと。何がおかしいの。そして、そのとき舞台上でおこなわれていること。お笑い観たかったら吉本行くって。テレビで十分か。どうしてダンスに「お笑いの要素」、しかもレベルの低い、を取り入れなくてはならないのか。
理解できない。
だけど、大橋可也&ダンサーズは笑えると思うよ。ありえないことを真剣にやっているからね。稽古場では笑いをこらえるのがたいへんだ。
いつもの公演では観客が黙って見ているのがおかしかったのだが、「CLOSURES」では、たくさん笑ってもらったようだ。ウチの会社のS君は笑いっぱなしだったな。笑いの対象がはっきりしていて分かりやすかったからだと思う。このことは勉強になった。笑いに限らず観客をどういう心理状態に持っていくか、ということは僕たちが考えなければならない重要なテーマである。
演出家の仕事 [ dance ]
僕は演出家という肩書きを使うことはない。作品のクレジットにも振付とだけしか書かない。構成・演出とか書く人もいるが、ダンスにおいては振付がそれらを含有するものだと思っているから。
とはいえ、作品を上演するに当たっては、演出という仕事が無くなるわけではない。
これまでの多くの作品においては、稽古から仕込み、ゲネプロ、本番と作品の制作過程と上演が切れることなく続いていて、かつ最後の本番も1日限りだったので、本番上演における演出家の仕事はほとんど無かったといってよい。
しかし、「CLOSURES」は久々に2日間、たった2日だが、に渡る公演だった。
日をまたがる上演において、稽古で何をすべきか、僕はやるべきことを怠っていたと思う。そのために2日目の上演は小さなずれが起きてしまった。
僕はプロの演出家ではないし、そうありたいと思ってもいないけれど、やるべきことは明確ではなくてはいけない。訓戒を込めてメモしておこう。
ヒューマンインスタレーション [ dance ]
僕の作品を見て、美術のインスタレーションをイメージする人もいる。僕は、美術については不勉強なので、インスタレーションの何たるかを正確には理解していないのだが、インスタレーションあるいはインストールという言葉には、僕なりの関連も見出せないことはない。
僕が作品の中でやっていることは、人間にある設定を施し、ある環境の下にインストールすることだと言ってもよい。設定には、動きや形、キャラクターなどがあるし、環境には照明や音楽などが含まれる。そこで、配置された人間に起きる内的な感情、配置からイメージされる関係性が、作品の中で大きな意味を占めている。
だから、ヒューマンインスタレーションという言葉でも表せるのかも知れない。
とはいえ、新しい言葉を使うまでもなく、空間配置、距離というものは、ダンスの、コミュニケーション全般のとも言ってよい、非常に重要な要素であり、それらに対するこだわりは、ダンスをより普遍化させる、普遍的な想像力を喚起させるための方法だと思う。
「ダンス」に拘る [ dance ]
僕たちの作品を見て、ダンスに見えない人もいるだろう。また、ダンス以外のカテゴリーとかジャンルに当てはめたい人もいるだろう。そのことは全然構わない。
しかし、僕たちがダンスに拘っていることは、まぎれもない事実である。それは、このサイトを見ても明らかだと思う。ひたすら、ダンスがどうのという話しか書いていないのではないか。「パフォーマンス」という言葉も使っているが、すごく限定的な意味で使っている。例えば、大橋可也のプロフィールでは、「パフォーマンス活動を始める」と書いているが、それは当時、参加していたグループがパフォーマンスと名乗っていたから、という理由であるからだし、他の場面では、上演すること、とほぼ同義に用いている。「身体表現」という言葉にいたっては、僕自身の文章には登場してきていない。
稽古場でもダンスの話しかしていないように思う。まあ、雑談はしないから当然かもしれない。僕はけっして体系的にダンスを学んだものではないが、ダンスの教養をベースに作品を作っているのは確かだし、それなりのダンス理論も持っているつもりだ。
では、僕たちが拘っているダンスとは何なのか。僕たちの活動の主題は「ダンスとは何か?」である、とはいつも公言していること。だから、その問いに答えるようとすると、無限ループに陥ってしまうわけだが、一つの見方は提示することは出来る。
それは、プロセスとしてのダンスである。
武藤氏のブログのコメントに書いた文章を引用しておく。
僕は自身の活動を「ダンス」と銘打っているし、「ダンス」に拘っています。しかしながら、「ダンス」を標榜しているわけではなく、「ダンス」を定義しようとしています。更にいえば、僕たちは「ダンス」をやっているのではなく、僕たちがやる、やろうとしていることが「ダンス」なのです。
これは分かりづらいと思うので、もう少しわかりやすく。
僕は「ダンス」という名称を使って自身の活動をおこなっているし、ダンスに拘っていることも間違いありません。しかしながら、その活動は、ダンスが持っている意味に従うものではなく、ダンスに新たな意味を見出そうとするものであると考えています。ある見方からすると、僕たちはダンスをしていないと言えるのかも知れません。しかし、僕たちは、僕たちが関わっているプロセス、それをダンスと呼ぼうとしているのです。
そして、同時に、そのダンスは、今ここにあるダンス=コンテンポラリーダンスに他ならない。
僕たちのダンスは、コンテンポラリーダンスです。
「ミヅチ」動画 [ dance ]
「明晰さは目の前の一点に過ぎない。」でも映像を担当してくれた岡崎文生氏のブログで、過去に彼らと共同作業によって制作した「ミヅチ」1997年北沢タウンホール上演版のダイジェスト映像が公開されています。
今思い返しても、映像と身体によるパフォーマンスとしては、映像を使うことの必然が明確に打ち出されていて、完成度も高いものです。一見すると、今の大橋可也&ダンサーズの作品より完成度は高く見えるかも知れません。個人的には、当時のマルチメディアパフォーマンス(?)の最先端、だったと思われる、Dumb Typeと比べても遜色の無い作品だったと思います。
当時、あまり評価が広まらなかったのは、主に制作的な問題だったと思っています。その点で僕たちの努力が足りなかったのでしょうが。いずれ、別の形態ででも発表する機会を持ちたいと思います。
「ミヅチ」作品情報
原案:山口多美子
絵画:亀井三千代
振付・出演:大橋可也
映像:NEO VISION(岡崎文生、山口多美子)
音楽:山賀静樹、藤原敏弘
上演日:1997年11月14,15日
上演時間:74分
会場:北沢タウンホール
※他に1999年ウエストエンドスタジオ上演版のほか、野外、アートイベント上演版あり
噛み合わない/ダンス批評をめぐって [ dance ]
先月から飛び飛びではあったが、木村覚氏のブログ上でコメントのやり取りをしていた。もし、これらのコメントを通読された方がいらっしゃるなら、率直にお詫びしたい。とても議論といえるものではないからだ。ブログのコメント欄が議論に適したものであるかどうかは措くとしても。
なぜ、議論になっていないか。一番の原因は、僕の最初のコメントの記述が若干シニカルというか、斜に構えたものだったので、木村氏に自己防衛的な態度をとらせてしまったことだろう。具体的にいえば、僕が取り上げた「招待状」について、木村氏は明らかに過剰な反応をとっている。メタファーとして挙げた商品/サービスについても、メタファーとしては受け入れられなかったようだ。その最初の僕の姿勢については反省します。
特に、ここに議論の結論めいたものを書くつもりはないが、僕がコメントを寄せた動機付けに関する記述を再掲しておく。いずれ、木村氏に限らず、議論を継続する機会を持ちたいと思う。
僕の思い込みですが、木村さんは、シンポジウムのアジェンダに「観客」「劇場」を挙げられているように、ダンスにおける、演者と観客、および、劇場外の社会との関係について、強い関心を持っていると思います。 その関心に、僕は一方的に共感していて、故にこうしてコメントなぞ書き込んだりしています。 ダンスを構成する、あらゆる関係性の連鎖、その中にダンス批評家は含まれないといけないのではないか。 ダンス批評は舞台上のダンスについて語る前に、語る主体自らと舞台および舞台外の社会との関係について語るすべきではないか。
前衛の系譜 [ dance ]
イタリア滞在中の嬉しい出来事の一つに、ボローニャ、Danza Urbanaフェスティバルでの國吉和子氏による講演があった。ちなみに、内野儀、桜井圭介の両氏も同フェスティバルに帯同し、講演をおこなっている。
國吉氏の講演は、日本の戦前から戦後にかけての現代舞踊の歴史を俯瞰するものだったが、単に歴史的な人物、出来事をなぞるのではなく、その時代における前衛の在り方、その精神を紹介していたと思う。
戦前では、村山知義の活動、戦後では、具体美術協会、そして土方巽を中心に紹介していた。
僕の活動は、もちろん方法論としては和栗由紀夫氏に教えを受けた舞踏に影響を受けているのは確かだが、特定の舞踊、ダンスの表現形式の延長線上にあるものだとは思っていないし、何かを受け継ごうという意思も持ち合わせていない。しかしながら、今という時代において前衛でありたいと思う気持ちは常にある。その点において、僕の活動は日本の前衛の系譜につらなるものであり、そうありたいと願う。
不思議なこと [ dance ]
僕の作品は社会、個人のネガティブな部分にフォーカスを当てたものだと捉えられることも多いし、そのように作っているという自覚もある。
ただ、観る人の中にには、ネガティブな部分に共感を持てない人も多い。
ひょっとすると、そのような人には、僕の作品は必要ないのかも知れない。
しかし、不思議なのは、普段社会に暮らしていて、葛藤や軋轢を、さらに身体の異常を感じているからこそ、芸術作品を作ろうとか、観ようとか思うのでないだろうか。
そのようなネガティブな意識、感情、身体感覚を持っていない人は、芸術に関わる必要はないと思う。
芸術の意義、芸術との関わりの動機付け、は、僕の中では明確だが、他の人たちにとってはどうなのだろうか。
日本での評価 [ dance ]
「明晰さは目の前の一点に過ぎない。」公演終了後、観に来ていただいた演劇ジャーナリストの堤広志さんが「日本では評価されないよね。」と言われた。
同じようなことは、これまでもよく言われているし、海外で評価されてから日本で活動をおこなった方が近道なのではないか、と言われることもある。
しかし、僕が自分の作品を観て欲しい人は、僕たちと同じ時間、空間を共有する人たちだ。つまり、今の日本人、あるいは日本で生活する人である。
何故なら、僕の作品は、僕たちが今、ここに、生きている問題を題材にしているのだし、その問題に共感できる人こそ、僕が望む観客なのだから。
明晰さを超える [ dance ]
「明晰さは目の前の一点に過ぎない。」では、作品の明晰さ、例えば、映像、音楽、照明などの要素とその組み合わせに気づいた人は多かったようだ。
しかし、その明晰さを超えるもの、について、気づいた人は確かにいる、が、少ないだろう。
タイトルは、気づく、そのために考える、ことを促すためであったのだが。
目で見ないで感じてくれればよい、と思う。
ただし、誰もがそれを実践できるわけではない。
どうやって導くか。
面白い [ dance ]
作品のことを「面白い」と言われて悪い気はしない。
とはいえ、批評をおこなう人に、面白かった、面白くなかった、などと言われても、ああそうですか、としか思いようがない。
作品は、意味があるか、ないか、のいずれかだ。
面白かったと思うなら、なぜ自分が面白い、と思うのかを、自らを含むコンテクストの内に見出してほしい。
構成がああだから、こうだから、面白い、などという言説は、考えることを放棄しているに等しい。
そんなことは見れば分かることだ。
分からない、分かっていない [ dance ]
僕の作品を見て「分からない」人は多い。
作品を評価してくれる人、批評家のような立場の人、でも、作品の意図を「分かっていない」人が多い。
もちろん、作品の意図を理解し感じた上で、評価してくれる人も確かにいるのだが。
以前は、分からない、分かっていない、ということは仕方ないと思っていた。
どう感じ、どう思うかは、観客の責務であって、作家が関わるものではないと思っていた。
見る側の感受性や問題意識が足りないのだと。
しかしながら、作品を作り続けてきたことで僕の意識も変わってきた。
大橋可也&ダンサーズ作品の意図、それは確かにあるし、今の社会にとって非常に重要なものだと思っている、への理解を断念することは、作家としての責任を放棄することではないだろうか。
作品が説明的である必要は無いが、作品についての説明は必要だろう。
ということで、作品について、まずは最新作「明晰さは目の前の一点に過ぎない。」について、の解説を書いていこうと思う。
更新は少しずつになると思うが、作品と僕たちの活動についての理解を深めるための一助となれば、幸いである。
見たいもの [ dance ]
僕は人に見せたいものではなく、自分が見たいものを作っているのだと思う。
僕が見たいものが他の人々にとっても見たいものでもあればよいと思うが。
僕が何が見たいのかということ、僕と僕以外の人が見たいもののギャップ、については今後、整理していこうと思う。
演劇は嫌い [ dance ]
ダンスも見に行かないのに、演劇も見に行くことはめったにないのだが、今年はチェルフィッチェの作品を見に行っている。一応、話題になっているらしいし、押さえておこうか、というぐらいの気持ちだったのだが、おかげで僕は演劇が嫌いということが分かった。
舞台を見に行くことで、効果があると思うことは、自分自身に集中できること。というのは、雑音に満ち溢れた日常と比べ、光と音がコントロールされた劇場は、自分に集中するために一番良い環境であると思う。そこでは、自分の感覚、思考を研ぎ澄ますことが出来る。だから、僕にとって良い舞台作品とは、その自分自身の内面的な出来事に彩りを与えてくれるものだと思う。
しかしながら、ここで問題は、モノを考えるには、常に言葉を使っているということ。つまり、頭の中では言葉を入り乱れている状態なわけだが、そこに舞台上の言葉が現れたときには、思考に集中するなど出来るわけがないのだ。
だから、言葉を中心とした舞台、それが演劇なのかどうか分からない、は、僕にとっては害でしかないし、存在意義がない。
更に不思議なのは、他の人にとって、演劇は存在意義があるのだろうか?
どうして、古来より演劇というものが存在してきたわけ?
さっぱり分かりません。
公演を見に行くこと [ dance ]
ほとんど、他人のダンスの公演を見に行くことはない。
理由の一つには、そもそも興味がないということがあるのだが、もう一つの理由として、狭い世界ゆえ、どうしても知人にあってしまうことになり、挨拶や会話をしなくてはいけないということがある。
会話自体が嫌いなわけではないのだが、疲れてしまうのです。
振付のメカニズム [ dance ]
コレオグラファー、振りを付ける人、によって振付をおこなう仕組みは異なるのだろうが、僕にとって、振りを付けるということは、自分の内的経験を投影することだといえる。投影するためには、ダンサー、振りを付けられる人、に対して感情移入をおこなう必要がある。今さらながら、そのことに気づいた。
ダンスとは、振付とは? [ dance ]
先日、インタビューを受ける機会があり、以下のように答えました。
ダンスとは、自己と他者とのコミュニケーションである。
では、自己とは誰か、何か、他者とは。それらを定義するのが振付であると。
疑問 トヨタコレオグラフィーアワード2006 [ dance ]
トヨタコレオグラフィーアワード2006ネクステージの出場者(ファイナリスト)が発表になった。
今回、出場者を選考した選考委員の方々には、大橋可也&ダンサーズもお世話になってきたし、彼らのこれまでのダンス界での尽力については尊敬の念を抱いている。しかしながら、今回の選考結果については、大きな疑問を抱かざるを得ないのだ。
このようなコンペティションにおいて、賞を与える、出場者を選考する、などの行為の意味は、アーティストと社会との関係性を操作する、ということである。その意味を選考委員はどれほど考えているのだろうか。
出場者に選ばれた、山賀ざくろ、正直なところ、僕は彼の作品に共感するところは無い。しかし、地方で地道に活動を続けている、その姿勢は高く評価されるべきだと思う。作家自身の真意は推し量る他ないが、彼のあるべき姿は、地元、群馬で毎週か毎月か、決まった場所、20-30名ぐらいのキャパシティが良い、で上演を続けることができ、それに一定の観客がついてくることだろう。そのような環境をつくるための支援をすること、こそが彼を評価することであって、パブリックシアターで上演することや、作品の制作費として200万円を貰うことではないと思う。
あるいは、白井剛、彼は才能ある作家なのだろう、多分。しかし、彼は既にパブリックシアターの主催公演に出演し、複数の団体から多額の助成金をもらっている作家である。彼がトヨタコレオグラフィーアワードで賞を受賞したとして、その状況に何か変化があるというのだろうか。助成金の額が増える、その必要がある、とでも言うのだろうか。
結局のところ、今回の選考基準は、面白い、面白くない、でしかないのだろう。
コンテンポラリーダンス、このアワードは特にコンテンポラリーダンスを謳っていないが、を広く紹介するためには、その選考基準も有効であったろう。
しかしながら、アワードの設立から5年を越す今とはなっては、そのような選考基準に基づくアワードは、ダンス全体にとって、もはや害でしかない。早く止めたほうがよい。
開かれた質問 [ dance ]
以前も触れたが、コーチングの本を読み始めた。面白い。
特に「開かれた質問」は「開かれた作品」を目指す僕たちにとっては、必要な考え方だろう。作品が問いを投げかけるだけであってはいけない、閉ざされた質問、つまり、はい、いいえで答えられるような質問、であってはいけない、と思う。でなければ、作品が観客にとって、いつまでも自分のものになることはないだろう。しかし、重要なことは、質問には答えがあることだ。観客は答えをその場で伝えてくれるわけではない。開かれた質問を続けるためには、答えを推測しておくことが必要になる。そう、質問と同時に答えも考えていかなくては。
それにしても、ビジネス系の書物は読みやすいし、分かりやすい。現場で役に立つことも多い。芸術だか美学だかの何に役に立つか分からない本とは、えらい違いだ。これからは毛嫌いすることなく、ビジネス系の本も読むことにしよう。とはいえ、役に立つ本というのは、ほとんど書いてあることは同じなのだ。そんなにいくつも優れたノウハウがあるはずもないのだから。
読書だけでないが、バランスが大事。ビジネスとアートそれぞれの第一線で働いている人間はそんなにいない。僕にとって意味のあるものを探そう。
評価基準 [ dance ]
最近はダンスの公演を観に行くことは、ほとんどない。以前はよく行っていたが、その理由は自分の作品に役立てるための勉強であった。今でも他のダンス作品を観ることで、考えることや学ぶことも多い。しかしながら、今は勉強の時期ではないと位置づけているため、行かない。単純に時間がない、という問題もあるが。それでも、たまには、もっぱら付き合いのためだが、観に行くこともある。
最近のダンスの作品を観て思うことだが、若く、健康で、経済的にも恵まれている、と見える、男女がいかに面白い動き、かたち、キャラクターを演じたとしても、そこに何の感動があるだろう。何の芸術的、すなわち、社会的、意味があるだろう。
ダンサー、振付家が考えるべきことは措くとして、観客は何を求めてダンス作品を観るのか。いや、観るべきか。観客はダンス作品を観ることの意味を、何も考えてはいない、何の基準も持っていないと思う。もちろん、すべての観客とはいえないだろうが。
評論家、と称される人、の果たしている役割は大きいと思う。彼らが何の基準も提示できていないのではないか。彼らは面白さについての語る言葉をもてあそんでいるのだけではないか。
ダンスに限らず、芸術作品の評価の基準は、面白いか、ではなくて、意味があるか、であるべきだろう。
付け加えると、芸術作品の曖昧な意味性を見いだし、具体的な意味に結びつけることが、評する、という作業なのだ。
ひとごと [ dance ]
何がおこなわれていようとも、それが自身のこととして捉えられない限りは、それはいつまでたってもひとごとであって、エンターテイメントなのである。
舞踏の振付の重要な要素として、主体と客体の同一視または転倒、という要素がある。その方法論を突き詰めていくことは、一つの道だと思う。
稽古の時間 [ dance ]
僕にとって、週に一度、時に二度、の稽古の時間というのは、一番楽しみな時間であるのだが、と同時に、一番疲れる時間でもある。なぜ、疲れるのかというと、僕以外の稽古参加者、すなわちダンサーたち、が退屈していないように、気を使って、やることと時間配分を考えているからなのである。気を使い過ぎかも知れない。また、その場をやり過ごそうとして、与えることに精一杯になってしまうこともある。引き出すことに腐心すべきだ。
そのようなことを考えて、コーチングの本なんかを読もうと思い立ったのだが、あの手の本は「成功」というキーワードに抵抗があって、読んでいない。成功は目的なんかではない。
かたち [ dance ]
人の形は背後によって造られる。背後とは、その人およびその人を取り巻く社会の現在の状況、そして歴史である。ダンスにおける形は常に背後の表れなのであって、形と背後との距離、空間的あるいは時間的な、が意味を生むのだ。
エンターテイメント [ dance ]
過日おこなったWIPの終了後の会話の中で、僕たちの作品がサディスティックあるいはマゾヒスティックな刺激を求める観客にとって一種のエンターテイメントとなっているのではないか、という指摘、その方の発言通りではない、があった。
確かにその通りだし、観客がより「ハードコア」な「過激」な表現を求めているのは事実だと思う。以前、参加したSPACダンスフェスティバル2004の終演後に審査員より「もっと過激なことを期待していました」などという発言を聞いたこともある。そのような人たちに「わかっていない」ということは容易い。実際のところ、彼らには何の思慮も考察も無いのだ、ハードコア、過激の何たるかについて。僕は、彼らを楽しませる、ホラーの役割を担うような、作品を作りたいわけではない。とはいえ、簡単にその意図を否定するわけにもいかないのである。
僕たちの作品『あなたがここにいてほしい』における「嘔吐」という事件は、ショックを与えるものであると同時に、サルトルを引くまでもなく、現代社会に生きる僕たちが日常的に感じる身体反応である。
僕はそのキャッチーさ、を意図して嘔吐を使っているし、そういった意味ではエンターテイメントの要素を自覚しているのも事実なのだ。
芸術作品には、わかり易さ、あるいは、わかり難さ、両者は人によって反応が異なるというだけで同じ意味である、が必要だ。僕たちの作品に特長的な過激と呼ばれる一面は、僕の嗜好、これもまた事実、でもあると同時に、人間性の本質の「表れ」であると思う。その過激さが僕の作品では、わかり易さとわかり難さを演出している。
その演出意図はある意味、「わかっていない」人を啓蒙する役割を担っているのだが、今後の僕たちに必要なものなのか、まだ結論はない。
ダンスと社会貢献 [ dance ]
僕がダンスをやっているのは、一義的には自分自身のためである。自分が満足できることが出来れば、それでよいと思う。
とはいえ、上演芸術としてのダンス作品を作り、公開するということ、および、ダンス作品を作るため人々と関わること、それは社会的活動に他ならない。さらにいえば、僕の活動に限ることなく、ダンスというものは本質的に社会の中にあり、社会の中で一定の役割を担ってきたものではないか。
そう考えると、Japan Contemporary Dance Network(JCDN)が「社会とダンスを結ぶ接着剤」であることをその設立趣旨として謳っているのは、言葉として矛盾しているといえる。ダンスと社会を切り離して考えること自体が不可能ではないのか。
# JCDNの存在意義を否定するものではないし、その活動は意味のあるものだと思うが
ダンスは社会に貢献するものでなくてはいけない、でなければ、その存在意義は無い、と思う。それは作品の内容において、社会的な意味を、社会問題を作品の主題にすべきという意味ではないが、持つべきである、ということだけではなく、その作品の成り立ち、方法、も含めて何らかの社会的意味を持つべきである、ということである。特に、「コンテンポラリー」を自認する、あるいは、そう捉えられている、作家は現代社会の問題と無自覚であって良い筈はない。
現代日本が抱える大きな問題として、若年労働者の就業に関する問題がある。若年労働者がしっかりとした職能を見につけないということは、日本という国の存亡に関わる問題であろう。
翻って、コンテンポラリーダンスを取り巻く環境を見れば、多くのダンサーたちはフリーターとして生活しているという現実がある。大橋可也&ダンサーズにしても、僕を除けば、皆アルバイト生活者だ。フリーターとしてであれ、経済的に自立しているのであれば、彼らに何らかの責がある、ということはいえないだろう。しかしながら、ダンスという環境が、若者たちが本来、職能を磨くべき貴重な時期に定職に付かない現象を、間接的に支援してしまっている、彼らに定職に付かない口実を与えてしまっていることも間違いない事実である。
ダンスが若者たちに一時的な自己満足を与えるものになってしまってはいけない。では、ダンスは、ダンスの環境は、どうあるべきか。大橋可也&ダンサーズに課せられた大きな課題の1つであると思う。
コミュニケーションとモチベーション [ dance ]
考えていることを文章にすることは大事なことです。
考える=言葉にすると同義なのだから、言葉に出来ない考えは存在し得ない。
ということで、今考えていることを徒然と書くことにします。
ダンスというのものは、結局のところ、コミュニケーションとモチベーションなのです。
ダンスに限らず、人間の生活は全部そうなのですが。
そう、人との関係性、具体的にはそれは他者との距離であり速度なのだが、と自身のやる気とそのゴール!だけが人間の生活を構成する全て=ダンスに違いない。
また続けます。





